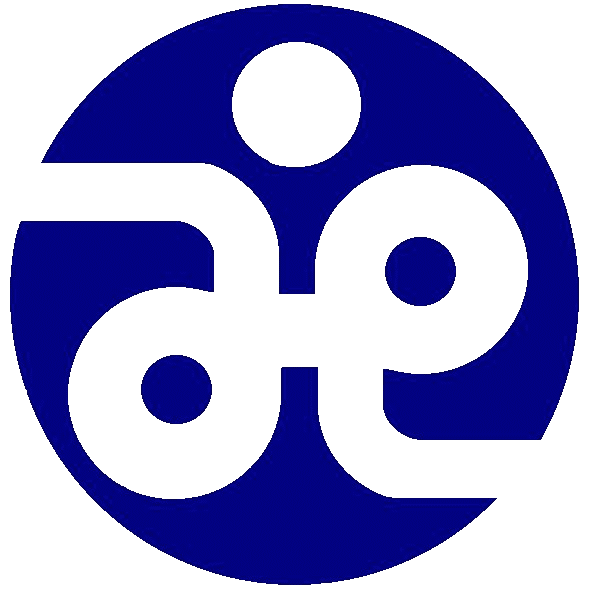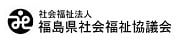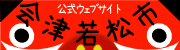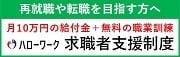会長のつぶやき
第五十二回
2022-10-03
高齢化社会の一端(いったん)を担(にな)っている私も、歳を重ねるに従い、友人・知人の訃報(ふほう)に接することが多くなりましたが、結婚式などの慶事に招かれることはなくなってしまいました。後は孫の結婚を待つのみです。(間に合うといいのですが。周りからは無理でしょうという声が・・・)
「80年かかってやっと手に入った80歳なのだから、大事に生きなければ」と思う半面、高齢者の多くは「つまらんようになった」と自嘲気味(じちょうぎみ)に本音をもらします。何故そう思わずにはいられないようになっているのか考えてみました。
「80年かかってやっと手に入った80歳なのだから、大事に生きなければ」と思う半面、高齢者の多くは「つまらんようになった」と自嘲気味(じちょうぎみ)に本音をもらします。何故そう思わずにはいられないようになっているのか考えてみました。
戦後77年、わが国は世界有数の高品質製品生産国になり、そのために、木材・石材・鋼材・集成材などあらゆる素材や用材が必要となりました。さらに、知恵も技術も労働も情報も資金もそのための「材」となり、そういうことから「逸材(いつざい)」「適材(てきざい)」「人材」などと、人間が「材」としての価値でみられるようになったのです。
確かに人生の中で、人材と呼ばれるにふさわしい働きをする時期はありますが、私たちは「人材」である前に、「人間」であることを明確にしておかなければなりません。
「人材」とは、何か(誰か)にとって役に立つ、あるいは都合の良い材料としての人間のことですから、いい人材からそうでもないものまで、はっきりと序列・順位が付きます。そして、その役や仕事のための人材として相応(ふさわ)しくなくなると、同じような働きをする他の人が人材として代わるわけです。つまり、人材は代行可能であり、見る人による価値の序列があるものです。
確かに人生の中で、人材と呼ばれるにふさわしい働きをする時期はありますが、私たちは「人材」である前に、「人間」であることを明確にしておかなければなりません。
「人材」とは、何か(誰か)にとって役に立つ、あるいは都合の良い材料としての人間のことですから、いい人材からそうでもないものまで、はっきりと序列・順位が付きます。そして、その役や仕事のための人材として相応(ふさわ)しくなくなると、同じような働きをする他の人が人材として代わるわけです。つまり、人材は代行可能であり、見る人による価値の序列があるものです。
私たちは、生きていれば必ず老い、傷病(しょうびょう)を得、死を迎えます。それに従って、世間的には人材としての価値が下がっていくとみられるので、「つまらん者になった」と嘆くことになります。若い元気な時に、老人や障がいのある人などを価値が低いと蔑視(べっし)していた人ほど、自分がそうなったときに、事実をまっすぐに受け容れにくいようです。
大事なことは、私たちは「人間」であるということです。人間である限り、いのちあるものである限り、無条件に尊いのです。その尊さは、老いや心身の傷病や肉体の不自由などでいささかも減ずるものではありません。全く平等の世界です。
完璧(かんぺき)な人も完成された人も一人もいない、みんな長短を併(あわ)せ持った者同士です。その表れ方はそれぞれで、それが個性となる。だからこそ誰も代わることはできません。不完全なそれぞれが、それぞれに尊く平等なのです。そして不完全であるからこそ、願われているのであり勉強する余地があるのです。成長し続けるのです。また、支え合い、助け合わなければ生きていけないのです。
宗教とか教育というものは、「人間」を育てるものであって、「人材」をつくるものではないのです。もちろん結果として、優れた人材として活躍する人と成ることは素晴らしいことですが、まず人間としてどう成長したかということが大事なことでしょう。
「ヒト」として生まれた私たちが、さまざまな学びと経験を通して、私に安心できる人間性豊かな、自覚的人間に成っていく。そういう必要性を背負って生きていると感じさせられています。