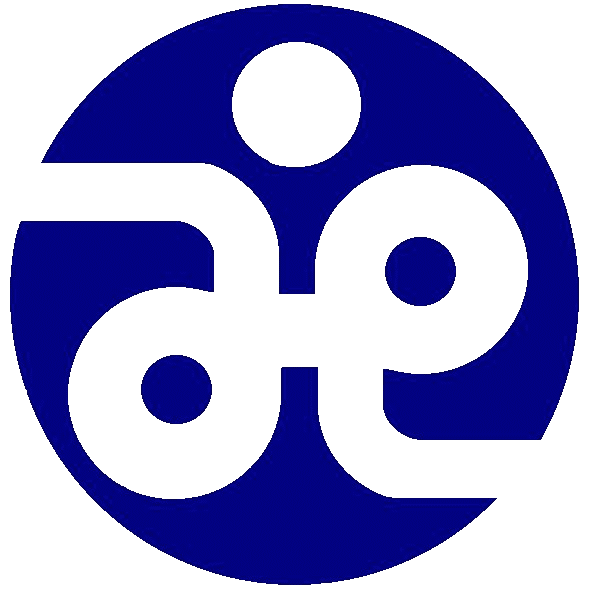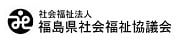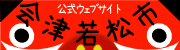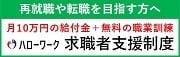会長のつぶやき
第五十三回
2022-11-02
先日、新入職員の歓迎の意味を込めた、昼食会を催(もよお)していただきました。コロナ感染の蔓延(まんえん)以来、全職員での歓送迎会を開げずにいることから、いつも幹事役を担(にな)っていいただいている職員さんの発案で、楽しい昼食の時間を用意していただきました。もちろん大勢参加の会食はできませんので、幹事さんの独断と偏見により厳選された(?)数名の職員での昼食会でした。和気(わき)あいあいとした雰囲気(ふんいき)の中で、おいしい昼食をご馳走(ちそう)になりました。
「食」とは、私たちのいのちと身心を養い育てて、保ち続けるものです。それぞれの「食」、が咀噌(そしゃく)され消化吸収されて、私の体といのちの一部になります。
「食」とは、私たちのいのちと身心を養い育てて、保ち続けるものです。それぞれの「食」、が咀噌(そしゃく)され消化吸収されて、私の体といのちの一部になります。
私たちが、人間として育ち成長していくのに何が必要でしょうか。口から入る食物のみではありません。知識・知恵・経験・情報、さまざまなモノ、また親や友人をはじめとする種々の人間関係(ふれあい)や思い出も大切です。そして、願われてある存在(いのち)であることに気づくことが、安心や元気につながります。
仏教では、私たちの生命維持(いじ)と成長に必要な、四つの「食」を教えています。これを「四食(しじき)」といいます。
仏教では、私たちの生命維持(いじ)と成長に必要な、四つの「食」を教えています。これを「四食(しじき)」といいます。
1、段食(だんじき) 一 一口一口の日々の飲食物のこと。肉や野菜などの実際の食物をいう。
2、触食(そくじき) 一 外界(げかい) とのとの接触(せっしょく)のこと。親鳥が卵を温かく抱くことで
2、触食(そくじき) 一 外界(げかい) とのとの接触(せっしょく)のこと。親鳥が卵を温かく抱くことで
雛(ひな)が孵化(ふか)し育つように、いのちあるものは温かい触れ合いによっ
て育ちます。
私たちは、よき人と、自然と、動植物などとの触れ合いに育てられています。
3、思食(しじき) 一 自分の意志や思考が身体や生命を養うということ。自分の成りたい状態を願い求
私たちは、よき人と、自然と、動植物などとの触れ合いに育てられています。
3、思食(しじき) 一 自分の意志や思考が身体や生命を養うということ。自分の成りたい状態を願い求
め、その意欲をもって自分を育てよう高めようという意思が、その人を育てると
いうこと。
4、識食(しきじき) 一 精神の主体(心)をいう。見たもの、聞いたこと、香り、味、感触とその内容を認識
4、識食(しきじき) 一 精神の主体(心)をいう。見たもの、聞いたこと、香り、味、感触とその内容を認識
し、満足や喜びや感動や感謝の心がはたらいて、私たちの「生きる」ことが成り立
ちます。
世界中に食事とその作法の文化があります。私たちのいのちを支え育てる、家庭や社会のなかでの大事な教育です。「不殺生(ふせっしょう)」が仏教徒の生活規範(きはん)の第一ではありますが、私たちは生きるために命あるものを食べなければなりません。野菜や果物は枯(か)れてしまってからでは食べられないし、肉や魚介(ぎょかい)も新鮮なものを求めますが、むやみに殺してはなりません。
食事の前に、眼前の食物や生物(いのち)に向って両の手を合わせ(合掌(がっしょう)一いのちに対する敬意(けいい))、申し訳ありませんが、私の生存のためにあなたのいのちを『いただきます!』と、言わずにおれない伝統のマナーを大事にしなげればならないと思います。
また、この食事が私の前に整うまでの過程と準備への感謝を込めて、手を合わせ『ごちそうさま!』も忘れてはなりません。
世界の国の中で下から14番目の食料自給率(42%)の日本で、食べ物の3割が捨てられているといわれています。
この現実もふまえながら、忘れかけていた豊かな食文化を思わずにはおれません。
世界中に食事とその作法の文化があります。私たちのいのちを支え育てる、家庭や社会のなかでの大事な教育です。「不殺生(ふせっしょう)」が仏教徒の生活規範(きはん)の第一ではありますが、私たちは生きるために命あるものを食べなければなりません。野菜や果物は枯(か)れてしまってからでは食べられないし、肉や魚介(ぎょかい)も新鮮なものを求めますが、むやみに殺してはなりません。
食事の前に、眼前の食物や生物(いのち)に向って両の手を合わせ(合掌(がっしょう)一いのちに対する敬意(けいい))、申し訳ありませんが、私の生存のためにあなたのいのちを『いただきます!』と、言わずにおれない伝統のマナーを大事にしなげればならないと思います。
また、この食事が私の前に整うまでの過程と準備への感謝を込めて、手を合わせ『ごちそうさま!』も忘れてはなりません。
世界の国の中で下から14番目の食料自給率(42%)の日本で、食べ物の3割が捨てられているといわれています。
この現実もふまえながら、忘れかけていた豊かな食文化を思わずにはおれません。