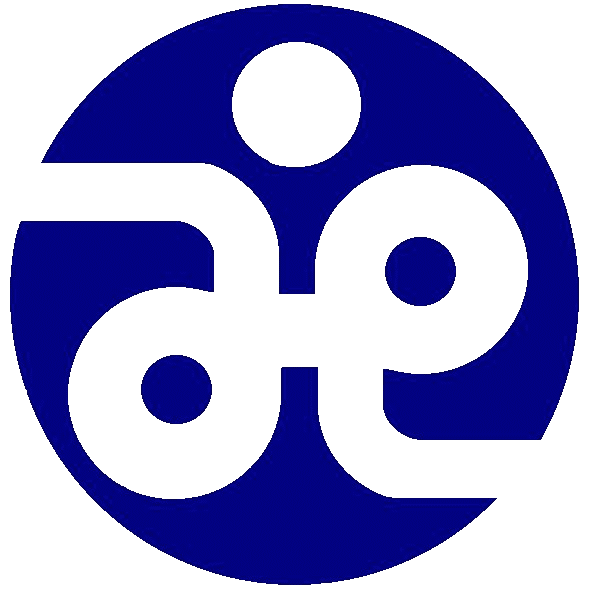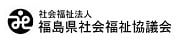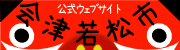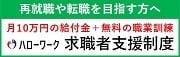会長のつぶやき
第二十六回
2020-03-11
「啐啄同時そったくどうじ」(鶏の卵がかえるとき、「啐」は殻からの内から雛ひながつつく、同時に「啄」は母鶏が殻の外から同じところをつつく)という言葉があります。
外からの刺激や情報と内からのはたらきの接点に、「学び」が実現するということを喩たとえた言葉で、師匠の教える力と共に生徒が「学ぶ力」を身につけなければ、十分に学力を身につけることができないということをあらわしています。
一口に「学力」と言いますが、「学力」とは何を指すのでしょう。
一般的には、どのくらい知識や技能を身につけたかという、結果としての「学んだ力」を指しています。
しかし、「学ぶ力」ということは、教わったこと出会ったこと与えられた情報などを、いかに力として吸収するか、身につけるかという力のことをいうのだと思います。
また、「学ぼうとする力」は関心の向きというか、意思をもってさらに学ぶ姿勢というか、そういうものでしょう。
自分では意識していない学びもあります。日常の生活の中で、知らず知らず染しみ込んでいく多くのことがあります。
例えば言葉の環境です。感謝や喜び、尊敬、信頼の言葉(ありがとう、いただきます、もったいない、おはよう、こんにちはなど…)の交わされる中に生活するのか、批判や愚痴ぐち、攻撃の言葉が飛び交う中で育つのか、大きな違いになっていきます。周りの大人たちがよく勉強すると子どもたちもよく勉強します。
「弟子の準備ができると、師が現れる」と言われます。学ぼうという意欲があり学ぶ力さえあれば、あらゆるものごとから気づき学ぶことを見つけて、そこから思惟しゅい(考えること)が始まり深まり、言動となります。
学ぶ姿勢とは、出会ったもの学んだことから自分自身を正しく知り、それによって自分の内にあるものが顕在化けんざいかする、すなわち生き方が変革することになっていく。生きる姿勢が変わるのです。
大人も子供も、今自分に与えられている能力資質感性を眠らせることなく、学ぶ姿勢をもって「啐啄同時そったくどうじ」の成長の瞬間を積み重ねてほしいものです。