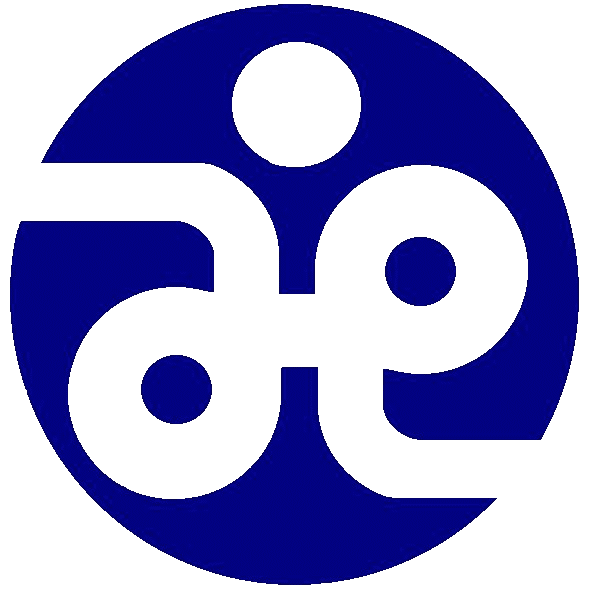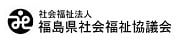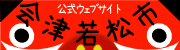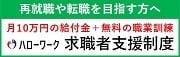会長のつぶやき
第六十回
2023-07-07
人口の増加が報ぜられる国がある一方で、世界有数の豊かな国である日本では、子供の数が減り続け、人口減少が心配されています。
私たちは、今日まで国を挙(あ)げて豊かさを求め走り続けてきました。そして日本中の都市化を目指し、個々人がそれぞれ自分の都合に合う環境条件を整えることで、そのことを実現させようとしてきました。その結果として「家庭」や「家族」の形態や考え方が大きく変化してきました。
昭和の初め頃はまだ珍しかった、サラリーマンと呼ばれる人が増え続け、男性は外で仕事、女性は専業(家事、育児)主婦ということが社会の「常識」のように考えられ、夫婦中心の核家族が一般的になりました。
それによって経済の成長は遂(と)げてきましたが、「人間の成長」ということに関して言えば、家庭や地域の教育力を低下させてきたように思います。
出産・育児・家庭教育・杜会教育が、極めてプライベートな問題(個人の都合に左右される)になってしまいました。祖父母でさえ関わりが少ない、そういう環境に子供が置かれています。
考えてみれば、女性にとって出産・育児は、生まれて初めての経験ですから不安を抱えるのは当然です。子供を育てるという大事業が、母親一人の手だけでできることではありません。その不安を、与えすぎやワガママ容認(ようにん)や過保護で対応してしまうと、子供の健全な成長は損(そこ)なわれがちになります。
基本的に出産・育児は、本来個人的に密室で行われるようなものではなく、パブリック(公)なことではないかと思います。関係するすべての人々が、その子の安全や成長に関心を払い、できる範囲でお手伝いをするという、かつてはどこにでもあった伝統的風景のように思います。
生まれた子供が、親の思い通りになるなどあり得ないことです。その不如意(ふにょい)(思い通りにならない)を経験しながら、親も子もともに「人間」になっていくのでしょう。子供が人間であるという事実と真正面からぶつかることが、親に人間であることを迫(せま)る。そうして子供が育つことを通して、家族やその周囲が絆を深め、大切にし合う関係を築きながら、社会が形成され維持(いじ)されていたのでしょう。それが、都市化・個別化の中で崩(くず)れてきたのが、今の社会の状況となっているのではないかと思われます。
少なくとも、個別に都合が満たされるほど価値があるという見方考え方を方向転換しない限り、少子化に歯止めがかからず、若い人たちの犯罪(罪の意識が希薄(きはく)で、本当に気軽(きがる)に行っているようにしか見えない)も減らないのではないかと思います。