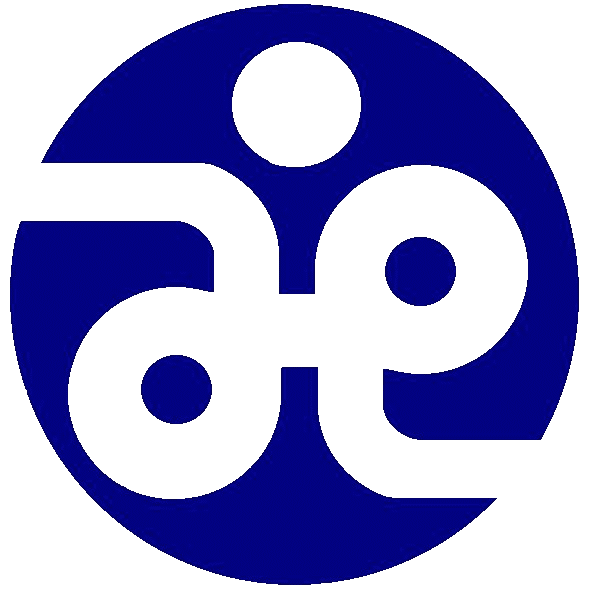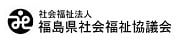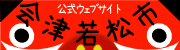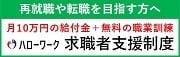会長のつぶやき
第七十回
2025-04-09
NEW
先日、毎日新聞の「カルチャースコープ」という特集記事を読み、改めて日本人と言葉について考える機会をいただきました。以前にもこのHPで言葉の大切な役割について書いたことがありましたが、今回は、劇作家・演出家としてご活躍されている、「わかぎゑふ」という方の文章を引用させていただきながら、特に「一人称」について考えてみたいと思います。
〇私たちは小学生に上がる頃に親や学校の先生から「男の子なんだから僕って言いなさい」「女の子だから、私って言うのよ」と、性別に合った一人称を使うように教わる。日本人は男言葉、女言葉をそれぞれ当たり前に使う。
他にも大人言葉、子供言葉、不良言葉、上流階級言葉――などいろいろあるが、誰も不思議に思ったことなどないだろう。
しかし、英語なら「アイ」で済む一人称がこんなにたくさんある国は他にないということに気が付いた時に、私は大いに考えた。日本語学者、金水 敏氏はこの自分の性別や身分を表す言葉を「役割語」と名付けている。
例えば見るからに高そうなスーツを着た素敵(すてき)な初老(しょろう)の男性が「私は医者です」と落ち着いた声で言えば「ああ、この人はお医者様なんだ」と周りもすぐに信用する。彼が医者という役割からはみ出さずに話しているからだ。
しかし「俺は医者だぜ」と荒っぽい言い方をしたら「え?何この人、本当に医者なの?」と疑うだろう。「あたし、お医者様よ」なんて言い出したら完全に混乱するに違いない。
確かに日本語の一人称は多種多様で、どの言葉を使うかによってその人の性別、立場、役割などを髣髴(ほうふつ)とさせろ働きがあるようです。
以前、長年アナウンサーの職にあった方の講演で、『一人称によって、そのあとに続く言葉が決まってくる。例えば「私」という言葉の後には「ご飯を食べました」あるいは「食事は済ませました」となり、決して「飯食った」とはなりません。』ということを聞いたことがあります。
このように、自分を表す一人称(役割語)は、「私」「僕」「俺」「あたし(あたい)」「うち」「わし」と多彩であると同時に、相手に何も説明しなくても自分の立場や性別などを表現できる誠に便利な言葉になっており、日本特有の文化となっています。
〇しかし、この便利さを裏側から見たら、人の立場を決めつけ、利用したり、閉じ込めたりしてはいないだろうか?ひいては日本のジェンダーフリー化を阻(はば)む大きな伽(かせ)になっていないだろうか?
近年知り合った一人の青年から、かつて自分が女の子であり、子供の頃に「私」と言わされることに苦しんだと聞いた。彼は心の底から「僕」という日を待っていた。両親を口説き、大変な手術を受け、名前を変え、戸籍を変更するまでの長い闘いを選んだ末に言えた「僕」という一人称は、彼にとって勲章のように輝いていたにちがいない。
一人称による文化の陰で、必要のない苦しみを抱えている人もいる。ことばとは本当に便利で恐ろしいものだとつくづく思う。(中略)
「僕」と「私」の間に流れる深くて大きな河を日本人はいつか渡れるのだろうか。誰もが同じ一人称で喋(しゃべ)るとしたら、いったい何が一番適していると思いますか?
この一人称に限らず、日本語の優れた働きの陰に、このような落とし穴が潜んでいたことに気づかされた思いです。皆様はどのように感じられたでしょうか。