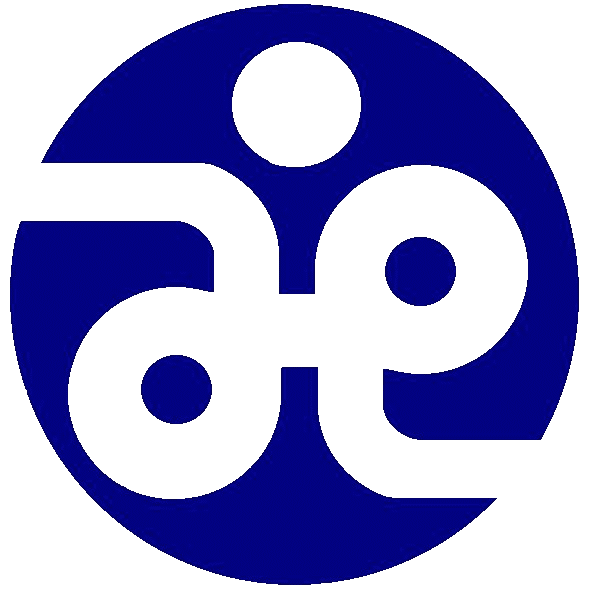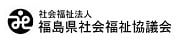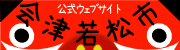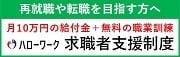会長のつぶやき
第十八回
2018-06-14
ものごとをプラス・マイナスに分けて、マイナスをどうプラスに受けとめ、解釈して転じるかという「プラス思考」がもてはやされているようです。
もともと西洋と東洋(特に日本)では、ものごとを受けとめる感覚が違っていたようで、明治以降西洋的思考(合理性重視)を受け入れるようになってから変化してきたようです。
西洋には雨か雪のどちらか一方だけで、雨と雪が混じって降る「霙(みぞれ)」という言葉・概念はないのだそうです。
「生死」━これは「しょうじ」と読み、ものごとの成り立ち(必ず変化する)を表す言葉で、執着しゅうちゃくする心から生まれる「迷いの世界」を言いますが、今は「せいし」と読み、「生」と「死」を分けて考えるようになりました。「生」は輝かしいプラスで、「死」はマイナスで避けて通りたいと、視界から遠ざけようとする傾向が強まり、「死」から学ぼうとする感覚が薄れてきたように思えます。
いわゆる「プラス思考」━志向ですが、その基準はいつも「その時の私の都合」です。事実は厳然たる事実であって、私にとってのプラス・マイナスの価値は相対的なものでしかありません。辛く悲しいことはマイナスで、楽しく嬉しいことはプラスということではないのです。プラス思考に縛られて、マイナス(に見えること)に価値がないと考えることこそ問題なのです。眼前がんぜんの現実をいかにプラスに解釈し直すかに腐心ふしんする前に、与えられた事実としてそのまま引き受け、そこから出発するのです。
一見マイナスに見えることから、私たちはいかに多くのことを教わり学ぶか。けがや病気をしてはじめて気がつくこと、大切な人を失ってはじめて目を覚まさせられること、高齢になってつくづく感じることなどがあるのでしょう。
実は私たちは互いに不完全同士ということで平等なのです。わが身に起こっていることが、自分にとって好ましくなく感じられることがあります。しかし私たちには、縁あってこの身に受けた現実は誰も代わってくれる者はいないのです。いないというより、代わることそのことがあり得ないことなのです。
たとえその時、辛く悲しいことであっても、本気で自分のこととして引き受け、しっかりと現実に立ち向かおうとするとき、勇気や元気が出てくるのです。出来ることは惜しまずやりましょう。本当にできないことはできないと認めて、くよくよ悩まず、手伝ってもらいましょう。