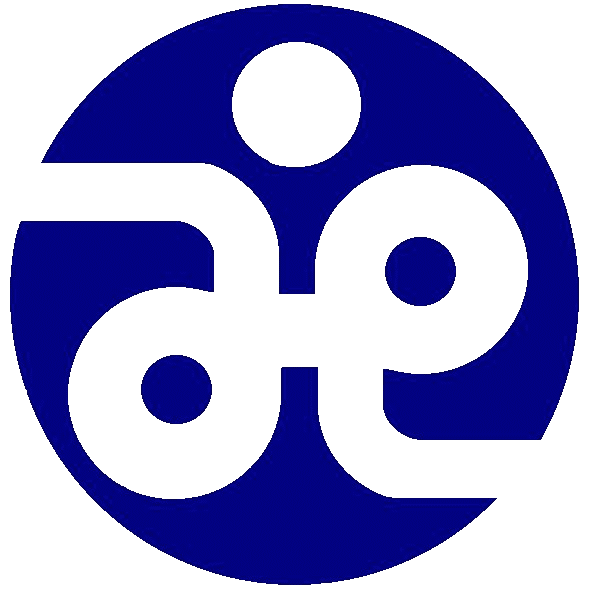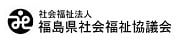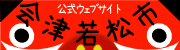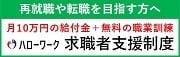会長のつぶやき
第三十三回
2021-03-02
「ことば」にはいのちがあるといわれます。
そういうことばから受ける「響き」というものを感じ取れなかったなら、そのことばはいのちを持たない死語となってしまいます。
生活の中に響いてくるものがなければ、それは死んだことば、新しいことばに直してみても決して生き返ることはありません。
しかし、それはことばの方に責任があるわけではありません。まして、ことばが死ぬわけでもありません。
それよりも、ことばそのものが持つ"ひびき"、この私の胸を打つそういう"世界"がなくてはならないのでしょう。そういうことを感じ取れる感覚が、この私に育っているかどうかの問題なのです。
この頃は、小学校、幼稚園、そして保育園でも英語の学習が取り入れられているようです。
ある日の孫(幼稚園年長組女の子)と私の会話。
「おじいちゃん、リンゴのこと英語でなんて言うか知ってる?」
「知ってるよ、"アップル"でしょう」
「ちがうちがう、"アポー"(発音どおりに書けません)だよ!」
「おじいちゃん、英語で"いただきます"ってどう言うの?」
「ん、………?」
英語のことはよくわからないのですが、多分「いただきます」ということばはないのでは、と思うのですがどうでしょうか。
日本には「いただきます、ごちそうさま、有難うございます、もったいない、お大事に、申し訳ありません、ごめんなさい、お恥ずかしい(ことです)」などという独特のことばがあります。
天地自然のはたらきを身に受けて、あらゆる生命(いのち)と共に生きていることを深い感動をもって受け止める、「いただく」「もったいない」「有難(ありがた)し(有ること難(かた)し)」などという言語表現は、日本人以外には無いのではないかと思うのです。
「私たちがものを考えたり行動したりする本(もと)となるのは、その人が積み重ねてきた生活習慣にある」といわれています。
どのような環境に生まれ、どのような育成を受け、どのような習慣を身につけたかが、その人の言動の本(もと)になるということでしょう。それほど日常の生活習慣は大きな意味を持つということなのだと思います。
人と人とを結び付ける大事なはたらきをする「ことば」を通して、私たちの感覚を育ててきた日本という国が、他の国に例を見ない独特の文化を築いてきたことを、いま改めて思い起こしていきたいと考えています。
そういうことばから受ける「響き」というものを感じ取れなかったなら、そのことばはいのちを持たない死語となってしまいます。
生活の中に響いてくるものがなければ、それは死んだことば、新しいことばに直してみても決して生き返ることはありません。
しかし、それはことばの方に責任があるわけではありません。まして、ことばが死ぬわけでもありません。
それよりも、ことばそのものが持つ"ひびき"、この私の胸を打つそういう"世界"がなくてはならないのでしょう。そういうことを感じ取れる感覚が、この私に育っているかどうかの問題なのです。
この頃は、小学校、幼稚園、そして保育園でも英語の学習が取り入れられているようです。
ある日の孫(幼稚園年長組女の子)と私の会話。
「おじいちゃん、リンゴのこと英語でなんて言うか知ってる?」
「知ってるよ、"アップル"でしょう」
「ちがうちがう、"アポー"(発音どおりに書けません)だよ!」
「おじいちゃん、英語で"いただきます"ってどう言うの?」
「ん、………?」
英語のことはよくわからないのですが、多分「いただきます」ということばはないのでは、と思うのですがどうでしょうか。
日本には「いただきます、ごちそうさま、有難うございます、もったいない、お大事に、申し訳ありません、ごめんなさい、お恥ずかしい(ことです)」などという独特のことばがあります。
天地自然のはたらきを身に受けて、あらゆる生命(いのち)と共に生きていることを深い感動をもって受け止める、「いただく」「もったいない」「有難(ありがた)し(有ること難(かた)し)」などという言語表現は、日本人以外には無いのではないかと思うのです。
「私たちがものを考えたり行動したりする本(もと)となるのは、その人が積み重ねてきた生活習慣にある」といわれています。
どのような環境に生まれ、どのような育成を受け、どのような習慣を身につけたかが、その人の言動の本(もと)になるということでしょう。それほど日常の生活習慣は大きな意味を持つということなのだと思います。
人と人とを結び付ける大事なはたらきをする「ことば」を通して、私たちの感覚を育ててきた日本という国が、他の国に例を見ない独特の文化を築いてきたことを、いま改めて思い起こしていきたいと考えています。