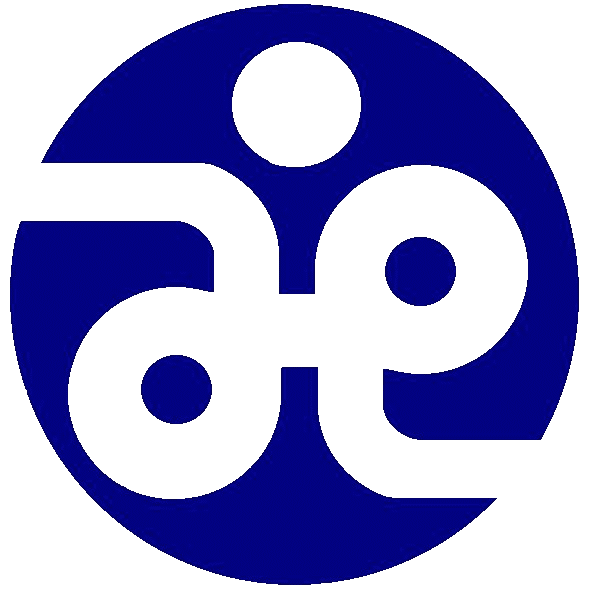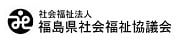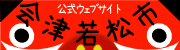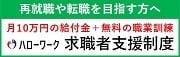会長のつぶやき
第五十七回
2023-03-16
「震災と戦争とはよく似ています」。1月に93歳で亡くなった作家で精神科医の加賀乙彦さんが「自伝」に記している。「どちらにおいても人間は自分の生きる場を奪われ、故郷を奪われ、ものもなくなり、当(あ)て所(ど)なくさまよい歩くしかない」。▲ロシアのウクライナ侵攻、トルコ・シリア大地震で苦しむ人々も同じだろう。10年以上内戦が続くシリアでは二つの苦しみがのしかかる。第二の都市アレッポでビルが倒壊し、lO人以上が亡くなったのは地震のl5日前だった。▲一時、反政府軍の拠点(きょてん)になり、激しい爆撃を受けた。多くの建物が損傷し、倒壊の危機性があったといわれる。そこに巨大地震だ。トルコ側に逃(のが)れた数百万のシリア難民も直撃を受けた。▲きようは東京大空襲から78年。あすは東日本大震災から12年を迎える。原発事故も戦争と同様に大災害級の被害をもたらす人災である。福島の人たちも二重の苦しみにさいなまれてきた。(以下中略)人々の痛みに思いをはせ、支援を続けたい。(3月10日付毎日新聞「余禄」掲載文)
私たちの周りの常識的な感覚として、他人に何かをしてもらうことは精神的負担であり、それにふさわしい何か(お礼など)で清算(せいさん)してバランスをとりたくなります。そのお返しが煩(わずら)わしいからと、困っていても他人に助けてもらうのをためらうことも少なくありません。
背の高い人は上の物をとるのに都合がよく、低い人は下の作業がしやすい、それだけのことです。そこに優劣も強弱もありません。みなできることとできないことのある者同士です。だから「お互いさま」と助け合う。「平等」とは、努力して勝ち取るものと思っていたら、それは自分の不完全さに気付き、そういう自分を引き受けてみると、既(すで)に開かれている世界でした。私たちは、本来平等であったのを、強がりと見栄(みえ)と浅知恵(あさぢえ)などで、差別の世界にしていたのです。大切なことは、自分のできることは惜しまずやり、できないことは、悩んだり気遣(きづかい)いし過ぎずにお願いすることです。
住む人が少なくなった状態を「過疎(かそ)」といいますが、周りに多くの人がいても、挨拶や言葉の交(か)わし合いがなくなれば、それが過疎(孤立化)となります。隣人を信じて安心して頼り合い、明るく豊かな共生を実現することが過疎の解消につながります。そしてそのことが私自身の生きている意味や価値を再確認する大切な場であると、喜びを得ながらコミュニケーションを回復していくことが大切なことだと思います。
本来ボランティアとは、無償(むしょう)の行為ということではなく、「自発的行為」という意味だと聞いたことがあります。
大切なのは、私たち自身の自発性や、「互いに、共に」という意識や意欲なのでしょう。互いにあらゆる人と関係し合いながら生きている私たちが、「人間」であり続けるために世話し合い、世話され合うという相互性が大事です。
「誰にも迷惑かけずに」といいますが、地球環境から言えば、人間が存在していることそのものが大変な迷惑なのです。公共のルールを守らないなどは論外ですが、問題は、迷惑をかけ続けて生きざるを得ない自分の「自覚」なのです。直接間接を問わず、世話になり合う安心感や信頼、相互敬愛(そうごけいあい)の豊かさを知り、互いにできることをし合いましょう。まず「ありがとう」の交換から始めましょう。