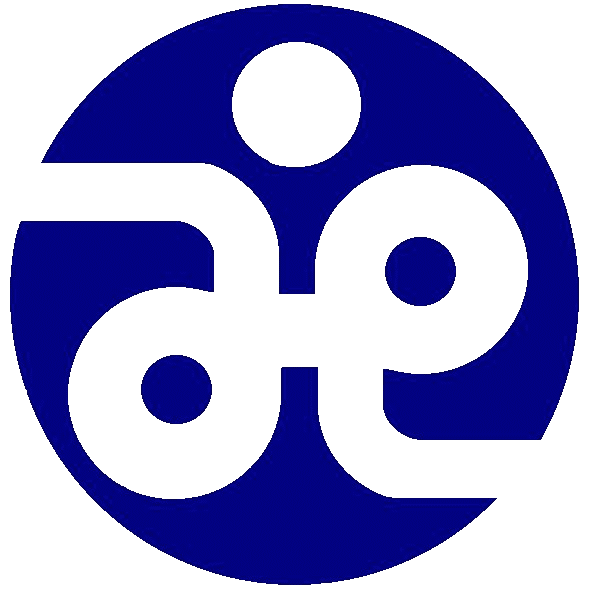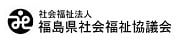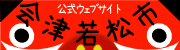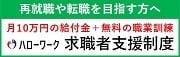会長のつぶやき
第五十八回
2023-04-21
最近立て続けに、年齢も近く、懇意にしていた方の葬儀に接する機会があり、「死」というものがより身近に感じられるようになりました。自分の年齢と重ね合わせて、改めて自分の人生や死のことを我が事として考えさせられています。
「われらは、ここにあって死ぬはずのものである。」と覚悟をしよう。ーこのことわりを他の人は知っていない。しかし、このことわりを知る人々があれば、争いはしずまる。(『法句経』(ほっくきょう)中村元訳)
私たちは、生きているのが素晴らしいと考えるあまり、死の意味を見逃してしまいがちです。「生きているときが花で、死んだらお終(しま)い」というような言葉も耳にします。現代人の死生観は、生のみの人生観になっているようです。それは、物事を自分にとって都合のいい面だけ見ていこうという姿勢で、いわば紙の表だけを求めようとするようなものです。
私たちが「人生」と呼んでいるものを仏教では「生死(しょうじ)」と表現します。それは生と死を併存(へいぞん)した人生観です。西洋でも「人間は死に向かって生きているものである」(ハイデッカー・哲学者)と言われるように、死を視野に入れて生を考えるのは当然のことであり、健康な人生観であるといえます。
言うまでもなく、どの人も皆死ぬ人です。例外はありません。絶対的真実といえるでしょう。人間は逞(たくま)しいものですが、またはかなく脆(もろ)いものです。そして自分自身のいのちがいつまで続くのか、いつどのような形で終わるのか、全く知り得ません。また計画することもできません。死ぬ者同士の私たちであると分かったとき、私たちが為すべきことは、支え合い、生かし合うことことのみでしょう。
心電図をとった方から聞いたことがあります。一日に10万回余の鼓動が記録されていたそうです。心臓が止まったら死ぬ私のその心臓は、今日までずっと動き続けて、私を生かしてきてくれました。眠っているときも働いているときも、気分のいい時も落ち込んでいるときも……。
「メメント・モリ」(死を想えと訳されていました)という言葉を聞いたことがあります。仏教的には「念死(ねんし)」(常に死から目を逸(そ)らすな)ということで、そのことがすなわち生を見つめることになるということです。
死の意味や人生における位置が明らかになると、生きている今の意味や価値も見えてきます。思い通りに生きることにのみ価値を見ようとする私たちには、老・病・死は「苦」ですが、死を見つめることで、私が私という人間として生まれ、亡き人も含め数多くの方々との関係の中で生きてきたことの自覚が生まれ、そこから満足や喜びが見出せるのではないかと思います。目を逸らし、老病死から逃げ回るような人生は、むしろ「生」がはっきりしません。死をごまかすと、生も実感できなくなるのです。
私たちは、身近な人の死に出会うと辛(つら)く悲しい思いを持ちますが、同時にその死を通してその人の生、つまりその日まで生きておられたここに一つの尊い人生があったということが、くっきりとしてきます。そこから、この私の人生も尊いものであったと、だから大事に丁寧(ていねい)に生きて、決して空(むな)しく過ごすようなことのないよう生きなければならないと知らされ、生きる楽しさや喜びも素直に感じられるのでしよう。
老病死をはじめ、イヤなことから目を逸(そ)らし避(さ)けようと、逃げ回っているだけが私の人生の姿となっていないか、問うていかねばならないと感じさせられています。