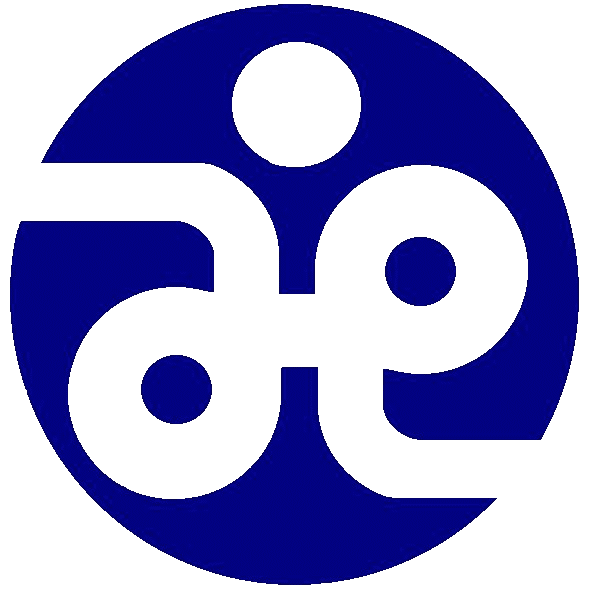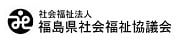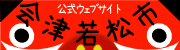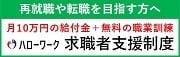会長のつぶやき
会長 武藤淳一
【生年月日】1942年(昭和17年)6月15日
【住まい】福島県会津若松市
【家族構成】妻、長男夫婦、孫2人の6人家族
【本職】寺院住職
【経歴】大学卒業後、教職を経て住職に。PTA役員、民生児童委員等を経験。
【住職として伝えたいこと】
「家庭」「生活」―人間として何をすること(ところ)なのかを学び実践すること
【仕事をする上で気をつけていること】丁寧(心を込めて親切に対応すること)
【座右の銘】身自當之しんじとうし無有代者むうだいしゃ(仏教の言葉)
意味:人生の中で苦しいこと、悲しいことに出会っても、誰も代わってくれないし自ら引き受けて生きていく
【尊敬する人】親鸞
【最近読んだ本】天地明察
第七十回
2025-04-09
NEW
先日、毎日新聞の「カルチャースコープ」という特集記事を読み、改めて日本人と言葉について考える機会をいただきました。以前にもこのHPで言葉の大切な役割について書いたことがありましたが、今回は、劇作家・演出家としてご活躍されている、「わかぎゑふ」という方の文章を引用させていただきながら、特に「一人称」について考えてみたいと思います。
〇私たちは小学生に上がる頃に親や学校の先生から「男の子なんだから僕って言いなさい」「女の子だから、私って言うのよ」と、性別に合った一人称を使うように教わる。日本人は男言葉、女言葉をそれぞれ当たり前に使う。
他にも大人言葉、子供言葉、不良言葉、上流階級言葉――などいろいろあるが、誰も不思議に思ったことなどないだろう。
しかし、英語なら「アイ」で済む一人称がこんなにたくさんある国は他にないということに気が付いた時に、私は大いに考えた。日本語学者、金水 敏氏はこの自分の性別や身分を表す言葉を「役割語」と名付けている。
例えば見るからに高そうなスーツを着た素敵(すてき)な初老(しょろう)の男性が「私は医者です」と落ち着いた声で言えば「ああ、この人はお医者様なんだ」と周りもすぐに信用する。彼が医者という役割からはみ出さずに話しているからだ。
しかし「俺は医者だぜ」と荒っぽい言い方をしたら「え?何この人、本当に医者なの?」と疑うだろう。「あたし、お医者様よ」なんて言い出したら完全に混乱するに違いない。
確かに日本語の一人称は多種多様で、どの言葉を使うかによってその人の性別、立場、役割などを髣髴(ほうふつ)とさせろ働きがあるようです。
以前、長年アナウンサーの職にあった方の講演で、『一人称によって、そのあとに続く言葉が決まってくる。例えば「私」という言葉の後には「ご飯を食べました」あるいは「食事は済ませました」となり、決して「飯食った」とはなりません。』ということを聞いたことがあります。
このように、自分を表す一人称(役割語)は、「私」「僕」「俺」「あたし(あたい)」「うち」「わし」と多彩であると同時に、相手に何も説明しなくても自分の立場や性別などを表現できる誠に便利な言葉になっており、日本特有の文化となっています。
〇しかし、この便利さを裏側から見たら、人の立場を決めつけ、利用したり、閉じ込めたりしてはいないだろうか?ひいては日本のジェンダーフリー化を阻(はば)む大きな伽(かせ)になっていないだろうか?
近年知り合った一人の青年から、かつて自分が女の子であり、子供の頃に「私」と言わされることに苦しんだと聞いた。彼は心の底から「僕」という日を待っていた。両親を口説き、大変な手術を受け、名前を変え、戸籍を変更するまでの長い闘いを選んだ末に言えた「僕」という一人称は、彼にとって勲章のように輝いていたにちがいない。
一人称による文化の陰で、必要のない苦しみを抱えている人もいる。ことばとは本当に便利で恐ろしいものだとつくづく思う。(中略)
「僕」と「私」の間に流れる深くて大きな河を日本人はいつか渡れるのだろうか。誰もが同じ一人称で喋(しゃべ)るとしたら、いったい何が一番適していると思いますか?
この一人称に限らず、日本語の優れた働きの陰に、このような落とし穴が潜んでいたことに気づかされた思いです。皆様はどのように感じられたでしょうか。
第六十九回
2025-01-20
新年明けましておめでとうございます。
元日早々に起きた大震災で始まった昨年は、残念ながら災害の多い年となってしまいました。
甚大な被害の復興もままならない状態で、この一年を過ごされた方々には、お慰めの言葉もありません。ただただ一日も早い復旧、復興を願うばかりです。
さて、昨年を振り返ってみますと、さまざまな社会状況の影響を強く受け、十分な成果を上げたとはいえない年になってしまったように思います。
新型コロナウイルスの感染もまだ終息には至らず、時折感染者の情報を耳にしました。加えてインフルエンザの流行もあり、予防対策は欠かせない状態でした。
少子高齢化が進む中、若い世代(中でも女性)の県外への転出が増加傾向にあり、県全体での人口減少が危惧されているようです。
また、核家族化による単身及び高齢世帯の増加による社会的孤立や生活困窮の問題も深刻化しています。その対策のひとつとしてのフードバンク事業も、生活協同組合コープあいづ様他、各企業や個人の方々の多大なるご協力によって何とかしのいでいるという状況にあります。
地球規模での大気汚染による気候への影響は、年々深刻さを増しています。いつ起こるかわからない災害への備えも心がけておかなければなりません。
この件につきましては、ライオンズクラブ国際協会332-D地区様より災害時対応備品及び収納用倉庫一式の寄贈を受け、北会津保健センター敷地内に設置させていただきました。災害発生時には大きな力となるものと、大変心強く感謝致しておるところであります。
このほかにも市民の皆様からは、折にふれ数多くの金品をお寄せいただき、事業運営に役立たせていただきましたこと、ここに厚く御礼を申し上げます。誠に有難うございました。
刻々と変化する社会情勢の中で、誰もが安心して暮らせるよう、地域で支え合える仕組みを創っていく「地域共生社会」の実現に向け、今年も皆様と共に歩んでまいりたいと考えております。
行政と一体となり、令和3年度より進めてまいりました「第2期会津若松市地域福祉計画、会津若松市社会福祉協議会地域福祉活動計画」は、令和7年度が最終年度となります。これまでの活動の成果を検証しつつ、さまざまな課題の克服に努めてまいりたいと思います。
計画の基本理念である「誰もが安心して暮らせるよう地域で支え合うあいづわかまつ」の実現に向けて、旧に倍する皆様のご協力ご支援を賜わりますようお願いを申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。
元日早々に起きた大震災で始まった昨年は、残念ながら災害の多い年となってしまいました。
甚大な被害の復興もままならない状態で、この一年を過ごされた方々には、お慰めの言葉もありません。ただただ一日も早い復旧、復興を願うばかりです。
さて、昨年を振り返ってみますと、さまざまな社会状況の影響を強く受け、十分な成果を上げたとはいえない年になってしまったように思います。
新型コロナウイルスの感染もまだ終息には至らず、時折感染者の情報を耳にしました。加えてインフルエンザの流行もあり、予防対策は欠かせない状態でした。
少子高齢化が進む中、若い世代(中でも女性)の県外への転出が増加傾向にあり、県全体での人口減少が危惧されているようです。
また、核家族化による単身及び高齢世帯の増加による社会的孤立や生活困窮の問題も深刻化しています。その対策のひとつとしてのフードバンク事業も、生活協同組合コープあいづ様他、各企業や個人の方々の多大なるご協力によって何とかしのいでいるという状況にあります。
地球規模での大気汚染による気候への影響は、年々深刻さを増しています。いつ起こるかわからない災害への備えも心がけておかなければなりません。
この件につきましては、ライオンズクラブ国際協会332-D地区様より災害時対応備品及び収納用倉庫一式の寄贈を受け、北会津保健センター敷地内に設置させていただきました。災害発生時には大きな力となるものと、大変心強く感謝致しておるところであります。
このほかにも市民の皆様からは、折にふれ数多くの金品をお寄せいただき、事業運営に役立たせていただきましたこと、ここに厚く御礼を申し上げます。誠に有難うございました。
刻々と変化する社会情勢の中で、誰もが安心して暮らせるよう、地域で支え合える仕組みを創っていく「地域共生社会」の実現に向け、今年も皆様と共に歩んでまいりたいと考えております。
行政と一体となり、令和3年度より進めてまいりました「第2期会津若松市地域福祉計画、会津若松市社会福祉協議会地域福祉活動計画」は、令和7年度が最終年度となります。これまでの活動の成果を検証しつつ、さまざまな課題の克服に努めてまいりたいと思います。
計画の基本理念である「誰もが安心して暮らせるよう地域で支え合うあいづわかまつ」の実現に向けて、旧に倍する皆様のご協力ご支援を賜わりますようお願いを申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。
第六十八回
2024-12-10
今年もあとわずかとなりました。年末を迎えると皆一様に来し方を振り返り、喜んだり悲しんだりしながら年の暮を過ごし、あたふたと新しい年に思いをはせ、次の年が良い年になるようにと「縁起物」に願いを託して祈りを捧げます。
この「縁起」という言葉は、釈尊(おしゃか様)が覚られた真理「縁起の理法」を指す言葉で、仏教の根本原理のことなのです。
縁起とは「縁によって起こる」ということで、あらゆるもの(こと)はその物事が単独で成り立つことはあり得ず、すべてが関係性の中で存在しているということを意味しています。
私たち一人ひとりも、もちろん関係性の中に生存しています。あらゆる物事は、すべてが関係し合い、補完(ほかん)し合い、相互に支え合って存在しているのです。私に関係ないものなどひとつもないのです。ことばを変えると、すべてはつながっているのです。私は私以外のすべてに支えられ、同時にすべてを支えているのです。
しかし、関係性の中にあるということは、物事は必ずしも自分の思い通りには進まないことを意味します。すべては認識することのできない諸々(もろもろ)の縁(条件)によって、現在も未来も成り立つわけですから、何事も自分の都合よくなどなるはずがありません。それを「不如意(ふにょい:意の如くならず)」と言います。
現代は「無痛(むつう)文化」とも言われ、苦痛の少ないことを価値と見ます。しかし共に生きるとは不如意を生きることです。摩擦(まさつ)も意見の違いもイヤなことも起こってきます。そこで自分の思いを通すことは、結局自他ともに苦しむ様相(ようそう)となっていきます。
生きる中で、自分の都合の良い人と別れ(愛別離苦(あいべつりく)・愛するものと別れなければならない苦しみ)、都合の悪い人と会わなければなりません(怨憎会苦(おんぞうえく)・恨んだり憎んだりするものと会わなければならない苦しみ)。必ずしも求めた通りの結果にはなりません(求不得苦(ぐふとくく)・求めて得ざる苦しみ)。それが現実です。ならば目を逸(そ)らさないことです。「思い通りにはならないが、なるようにはなる」のです。
私も年を重ねることで気付かされたことですが、人間は二つの知恵をいただいていると思います。
一つは加齢とともに衰(おとろ)えていく知恵です。記憶に関することや、新しい物事に対応する知恵です。そこばかりを気にかけて嘆(なげ)きますが、もう一つの知恵があるようです。
それは、加齢とともに深まっていく知恵です。不如意の現実を生き抜く中で、苦しみ、悩み、傷つき、考え、振り返り、自他を責めたりしながら深まっていくものの見方、受けとめ方、考え方などです。
その中から私が私に生まれたこと、生きること、老いること、病(や)むこと、死ぬことなどを考え、夫婦とは、親子とは、自分とは、他者とは・・・等々の問いを常に抱え、折に触れて感じること、思いつくことなどを味わうことになります。
不如意の現実をきちんと受け止めることが、目覚めのスタートです。思い通りにならない現実から逃避(とうひ)せず、そこで感じ考える、そのことが私を本当の私にしてくれるのでしょう。
この「縁起」という言葉は、釈尊(おしゃか様)が覚られた真理「縁起の理法」を指す言葉で、仏教の根本原理のことなのです。
縁起とは「縁によって起こる」ということで、あらゆるもの(こと)はその物事が単独で成り立つことはあり得ず、すべてが関係性の中で存在しているということを意味しています。
私たち一人ひとりも、もちろん関係性の中に生存しています。あらゆる物事は、すべてが関係し合い、補完(ほかん)し合い、相互に支え合って存在しているのです。私に関係ないものなどひとつもないのです。ことばを変えると、すべてはつながっているのです。私は私以外のすべてに支えられ、同時にすべてを支えているのです。
しかし、関係性の中にあるということは、物事は必ずしも自分の思い通りには進まないことを意味します。すべては認識することのできない諸々(もろもろ)の縁(条件)によって、現在も未来も成り立つわけですから、何事も自分の都合よくなどなるはずがありません。それを「不如意(ふにょい:意の如くならず)」と言います。
現代は「無痛(むつう)文化」とも言われ、苦痛の少ないことを価値と見ます。しかし共に生きるとは不如意を生きることです。摩擦(まさつ)も意見の違いもイヤなことも起こってきます。そこで自分の思いを通すことは、結局自他ともに苦しむ様相(ようそう)となっていきます。
生きる中で、自分の都合の良い人と別れ(愛別離苦(あいべつりく)・愛するものと別れなければならない苦しみ)、都合の悪い人と会わなければなりません(怨憎会苦(おんぞうえく)・恨んだり憎んだりするものと会わなければならない苦しみ)。必ずしも求めた通りの結果にはなりません(求不得苦(ぐふとくく)・求めて得ざる苦しみ)。それが現実です。ならば目を逸(そ)らさないことです。「思い通りにはならないが、なるようにはなる」のです。
私も年を重ねることで気付かされたことですが、人間は二つの知恵をいただいていると思います。
一つは加齢とともに衰(おとろ)えていく知恵です。記憶に関することや、新しい物事に対応する知恵です。そこばかりを気にかけて嘆(なげ)きますが、もう一つの知恵があるようです。
それは、加齢とともに深まっていく知恵です。不如意の現実を生き抜く中で、苦しみ、悩み、傷つき、考え、振り返り、自他を責めたりしながら深まっていくものの見方、受けとめ方、考え方などです。
その中から私が私に生まれたこと、生きること、老いること、病(や)むこと、死ぬことなどを考え、夫婦とは、親子とは、自分とは、他者とは・・・等々の問いを常に抱え、折に触れて感じること、思いつくことなどを味わうことになります。
不如意の現実をきちんと受け止めることが、目覚めのスタートです。思い通りにならない現実から逃避(とうひ)せず、そこで感じ考える、そのことが私を本当の私にしてくれるのでしょう。
第六十七回
2024-11-08
2024(令和6)年11月6日(水)付、毎日新聞社会面記事の全見出し語一覧
○強盗夫婦で「闇バイト」か
横浜・国分寺 現金『回収役』疑い
○容疑者夫?防犯カメラに
○国分寺でも勧誘か 所沢の「リクルーター」
○葛飾の強盗致死 新たに23歳逮捕
○高齢女性狙い10億円被害
カンボジア拠点特殊詐欺29道府県で
○危険運転致死争う姿勢
大分194キロ死亡事故被告側 地裁初公判
○萩生田氏の秘書裏金不起訴不当 検察審査会
○国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)の理事長が部下にパワハラ 大阪・異動迫る
○わいせつ容疑で市長を書類送検(沖縄・南城)
このところ首都圏を中心に、相次ぐ強盗などの事件は、8月〜11月にかけて計245件に及び、その一覧表が同紙に掲載されていました。
葛飾の事件で逮捕された23歳の容疑者は、「X(旧ツイッター)で『即日バイト』と検索し、ダイレクトメッセージを送った。人の家に入って物を取ってきてほしいと指示され、拒否したが脅された」という趣旨の供述をしているという。警視庁は「闇バイト」に応募したとみて、相次ぐ強盗などとの関連を調べている。
若者が、安易に大金が入るという「闇バイト」の誘いに応じてしまい、犯罪に手を染めてしまうという事件の頻発(ひんぱつ)には、ただただ驚くばかりである。20代、30代の若者が、一瞬の気の迷い(?)から、自分の手で自らの一生に消し去ることのできない「キズ」をつけてしまい、その罪を背負ってその後の人生をどう生きていくのか、悔やんでも悔やみきれない思いであろうと思います。
「懺悔(ざんげ)」「慚愧(ざんき)」という仏教の言葉があります。懺悔は一般に「ざんげ」と読まれていますが、仏教語の読みは「さんげ」で、「罪を自覚し、心から悔い改める」の意、慚愧は、「取り返しのつかないことをしたと強く悔やむとともに、自ら恥じる」という意味です。
自分の犯した罪を認め、悔やんだり恥じたりするどころか、何とか罪を逃れるためにあらゆる手を使って言い逃れをしようとする気風が、今の社会を覆っているように思われます。
多発する、詐欺・窃盗・強盗・傷害・殺人また各種のハラスメント・裏金問題などのあさましい事件は、私たちが人として本来身につけるべき、「懺悔」する心「慚愧」の心を見失ってしまったことにあるのではないかと思えてなりません。
廉恥(れんち) =(廉は、分限を知り利欲の念がない意)
心が清らかで、恥じるべきことを知っていること
(反対語 破廉恥(はれんち)=およそ恥ということを知らない意で、不正を行っても平気でいる様子)
潔(いさぎよ)い=未練がましくわが身の保身に囚われたりすることなく事に臨む心構えをいだく様子
このような言葉や心はもはや死語となってしまったのだろうか・・・
第六十六回
2024-10-02
今年は新年早々大地震に見舞われ、あろうことか同じ地域で大洪水の被害を被(こうむ)るという、未曾有(みぞう)の大惨事が起こってしまいました。二つの大災害を受けた能登地方の方々にはお慰めする言葉もありません。ただそれぞれが出来る限りのことをして復興を願うのみです。
近年の雨の降り方は、線状降水帯の発生による局地的な大雨により、各地に多大な被害をもたらすという特徴があるようです。
私たちがより便利で快適な生活を限りなく追い求め、一部の国が豊かな暮らしを謳歌(おうか)するために大気を汚し自然を破壊し続けています。その結果としてもたらされた地球規模での気候変動や自然環境の変化が、地球上のあらゆる生き物の生存を危(あや)うくしている状況を作っているのでしょう。
そのような危機的状況をよそに国際社会では、各国間の利害関係をめぐるエゴや主義の違いから、泥沼とも言える戦争・紛争が、いつ果てるともしれず続けられ、国民にはかり知れない苦痛と悲しみ、絶望感をもたらしています。
『忿(こころのいかり)を絶(た)ち、瞋(おもえりのいかり)を棄(す)て、人の違(たが)うことを怒(いか)らざれ。人皆、心有り。心各(おの)おの執(と)れること有。彼是(よみ)すれば則ち我は非(あしみ)す。我是(よみ)すれば則ち彼は非(あしみ)す。我、必ず聖に非ず。彼必ず愚(おろ)かなるに非(あら)ず。共にこれ凡夫(ただひと)ならくのみ。是(よく)・非(あしき)の理(ことわり)、詎(たれ)か能(よ)く定むべけん。相共に賢く愚かなること鐶(みみかね)の端(はし)無きが如し。是(これ)を以て、彼人(かれひと)、瞋(いか)ると雖(いえど)も、還(かえ)りて我が失(あやまち)を恐れよ。我独り得たりと雖(いえど)も衆(もろもろ)に従いて同じく挙(おこな)え。』
【意訳】(心に起こる)気にそまないことを憤(いきどお)る心を抑(おさ)え、思い込みによる怒りを離れ、人のあやまちに腹を立ててはならない。人はそれぞれに思いや考えがある。人の心にはそれぞれに執着(しゅうちゃく・こだわり)がある。人を良し(正しい)とすれば自分の思いは悪し(誤り)となり、自分を良しとすれば人を悪しとする。自分はけっして聖人(間違いのない人間)ではない。相手もまた愚かな(間違いだけの)人間ではない。お互い是(良し〉・非(悪し)両方を持つ人間同士なのである。是非(善悪、良し悪し)の道理をどうして判定など出来ようか。共に賢く愚かであることは、鐶(かん・金属の丸い輪)の端(はし)がないようなものである。このことを心得て、人が腹を立てたとしても、我が身を振り返り過(あやま)ちがないかどうかを気にかけよ。自分が得心(とくしん)したとしても、周りの人と協調して行いなさい。
この言葉は、聖徳太子の「十七条憲法、第十条」によるものですが、聞きなれない言葉だと思います。しかしこの教えは、国民不在の混迷する現代社会に一石を投ずる言葉ではないかと思われますので紹介します。
聖徳太子は、高慢心(こうまんしん)を戒(いまし)め、人間はともどもに善悪、良し悪しを併(あわ)せ持つ人間であるということで「平等」なのであるという真理を説いておられます。
私たちは、己に執(しゅう)することで相手を貶(おとし)めたり卑(いや)しめたり、時には排除しようとしたりします。お互いが「愚かさ」を謙虚(けんきょ)に認め「敬愛」の心で接したいものです。
『怨(うら)みは怨みによって止(や)むことはない。怨みを棄(す)ててこそ止む。』(釈尊の「前生物語」より)