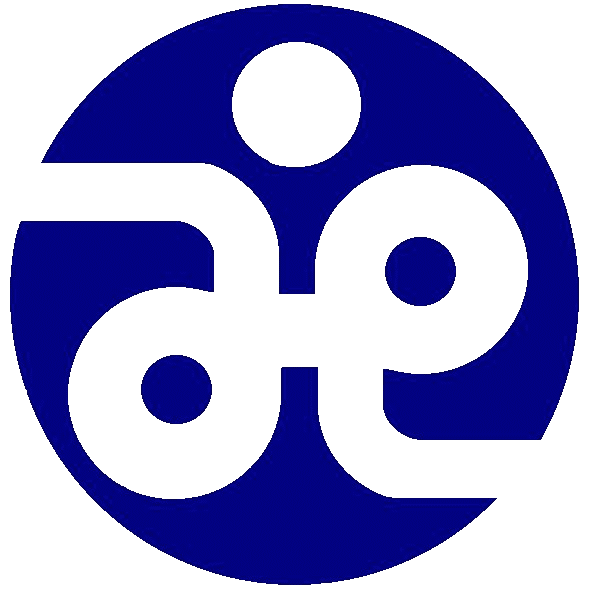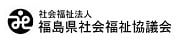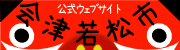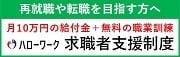会長のつぶやき
会長 武藤淳一
【生年月日】1942年(昭和17年)6月15日
【住まい】福島県会津若松市
【家族構成】妻、長男夫婦、孫2人の6人家族
【本職】寺院住職
【経歴】大学卒業後、教職を経て住職に。PTA役員、民生児童委員等を経験。
【住職として伝えたいこと】
「家庭」「生活」―人間として何をすること(ところ)なのかを学び実践すること
【仕事をする上で気をつけていること】丁寧(心を込めて親切に対応すること)
【座右の銘】身自當之しんじとうし無有代者むうだいしゃ(仏教の言葉)
意味:人生の中で苦しいこと、悲しいことに出会っても、誰も代わってくれないし自ら引き受けて生きていく
【尊敬する人】親鸞
【最近読んだ本】天地明察
第三十五回
2021-05-12
コロナウイルス感染が止まりません。会津若松市でも感染者の数が急増し、その数が連日報道されています。自粛生活も長引き、精神的にも経済的にもその影響の大きさは、日に日に深刻(しんこく)さを増してきているようです。後はワクチン接種の効果を期待するしかない、という状況のようです。
近年、世界中でその傾向が顕著(けんちょ)になり、さらにこのコロナ禍の中で一層強調されているように感じられるのが「個人の自由」ということです。
特に日本では、戦後「民主主義」に基づく教育や社会風潮の中で、「個性の尊重や伸長」が大きく言われてきましたが、その個性とかその背景にある自由ということをもう一度吟味(ぎんみ)してみる必要があると思います。
「個性」とは、本来その人に備わっている人格が表れ出たものだと思います。ですから、結果としての「個性」が発揮されるためには、その前提になる人格・発想・価値観などが問われなければなりません。はたしてこの私に「個人」がしっかり確立しているでしょうか?
また「自由」ということも、己(おのれ)さえよければ他人の迷惑など問題でない、という自分勝手なワガママを通すことが自由であるかのように思われがちですが、欧米の近代への歴史の中で、それこそいのちと引き換えに獲得(かくとく)した、「厳粛(げんしゅく)で尊い権利」なのです。
テレビやゲームに夢中になり時間を忘れることが自由なのでしょうか。緊急事態宣言の中、県外にまで遊びに出かけたり、深夜まで飲み会をしたり、マスク着用を拒否することが自由なのでしょうか。ただ単に自分勝手な主義主張に囚(とら)われ、振り回されているだけなのではないのか・・・。
ある先生の言葉が印象に残っています。
「自由とは、人間が本来どうしてもしなければならないことが、何者にも、どんなことにも妨(さまた)げられずにできる権利である」
ヒトとして生まれた者は、人間に成り、人間として共に生きるために、本来しなければならないことがある。それを自らの責任ではない束縛(そくばく)や強制(きょうせい)などによって、また、性別や年齢、貧富(ひんぷ)、国籍等々によって妨(さまた)げられてはならない。そういう権利があるということでしょう。
何を実現するための自由であるのか、またどういう自分が発露(はつろ)された個性であるのか。個性だと思っていて、実は流行や他人の眼に縛(しば)られて少しも自由でない私ではないのか。本当に尊い自由をはき違えてはいないのか、真剣に考えてみなければならないのではないかと思います。
第三十四回
2021-04-02
いま世界各地では、人種差別や性差別による人権侵害の問題が起こっています。内戦による避難民の悲惨な状況、少数民族への弾圧(だんあつ)や迫害(はくがい)、国民を守るためにある軍隊や警察が、こともあろうに自国の民(たみ)に向って武器を使用し、多くの死傷者を出すという出来事に、驚きとともにやりきれない思いにさせられています。
国内でも、施設職員による障がいを持つ人たちへ、また職場の上司による部下へのセクハラやパワハラ、いじめ、嫌(いや)がらせなどの多発、家庭内では子供への虐待、妻へのDV等、人を傷つける行為が頻繁(ひんぱん)に起こっています。また、コロナ感染の不安やストレスから、心無い言動が増えるなど、私たちの生活に暗い影を落としています。
私たちは、自分が幸せかどうかをどうやって確かめているのでしょうか。周りを見回してあの人よりはましだとか、あの人にはかなわないだとか、他人と比べないと幸せかどうかさえ分からないような状態になっていないでしょうか。
ひょっとすると私たちの幸せは、自分より下の人を見て初めて成り立つ(逆を言えば人より下になれば不幸)と思っているのではないか。だからいつも他人と比べずにはいられないのでしよう。
学校でも社会生活上でも個性を尊重するといいながら、その個性と思っているものが、実は同じ質のものが集まった中での強弱や、優劣、大小、勝ち負け、老若、健病などの違いでしかないということになっているのではないでしようか。
同じ質ということは、本来人間にはあり得ないことです。一人ひとりは全く独立の一人ひとりであり、他人とは違うのです。違っていいし、当然だし、違うことでしか成り立たないのです。
幸せは、他人と比べて確かめるものではありませんし、ましてや誰かが従属的(じゅうぞくてき)になり、我慢(がまん)をすることで成り立つようなものではないのです。
周りがどうであろうと、私が私であることを通して幸せであると実感できるかどうか、そのことが問われるのでしょう。
明珠在掌=みょうじゅ(何ものにも代えがたい宝物、幸せ)たなごころにあり(すでに自分の手の中にある)
私が私に安心して、他の人と共にいきいきと生きていける、どの人も居ていいんだという、そういうあり方を確かめていきたいものです。
第三十三回
2021-03-02
「ことば」にはいのちがあるといわれます。
そういうことばから受ける「響き」というものを感じ取れなかったなら、そのことばはいのちを持たない死語となってしまいます。
生活の中に響いてくるものがなければ、それは死んだことば、新しいことばに直してみても決して生き返ることはありません。
しかし、それはことばの方に責任があるわけではありません。まして、ことばが死ぬわけでもありません。
それよりも、ことばそのものが持つ"ひびき"、この私の胸を打つそういう"世界"がなくてはならないのでしょう。そういうことを感じ取れる感覚が、この私に育っているかどうかの問題なのです。
この頃は、小学校、幼稚園、そして保育園でも英語の学習が取り入れられているようです。
ある日の孫(幼稚園年長組女の子)と私の会話。
「おじいちゃん、リンゴのこと英語でなんて言うか知ってる?」
「知ってるよ、"アップル"でしょう」
「ちがうちがう、"アポー"(発音どおりに書けません)だよ!」
「おじいちゃん、英語で"いただきます"ってどう言うの?」
「ん、………?」
英語のことはよくわからないのですが、多分「いただきます」ということばはないのでは、と思うのですがどうでしょうか。
日本には「いただきます、ごちそうさま、有難うございます、もったいない、お大事に、申し訳ありません、ごめんなさい、お恥ずかしい(ことです)」などという独特のことばがあります。
天地自然のはたらきを身に受けて、あらゆる生命(いのち)と共に生きていることを深い感動をもって受け止める、「いただく」「もったいない」「有難(ありがた)し(有ること難(かた)し)」などという言語表現は、日本人以外には無いのではないかと思うのです。
「私たちがものを考えたり行動したりする本(もと)となるのは、その人が積み重ねてきた生活習慣にある」といわれています。
どのような環境に生まれ、どのような育成を受け、どのような習慣を身につけたかが、その人の言動の本(もと)になるということでしょう。それほど日常の生活習慣は大きな意味を持つということなのだと思います。
人と人とを結び付ける大事なはたらきをする「ことば」を通して、私たちの感覚を育ててきた日本という国が、他の国に例を見ない独特の文化を築いてきたことを、いま改めて思い起こしていきたいと考えています。
そういうことばから受ける「響き」というものを感じ取れなかったなら、そのことばはいのちを持たない死語となってしまいます。
生活の中に響いてくるものがなければ、それは死んだことば、新しいことばに直してみても決して生き返ることはありません。
しかし、それはことばの方に責任があるわけではありません。まして、ことばが死ぬわけでもありません。
それよりも、ことばそのものが持つ"ひびき"、この私の胸を打つそういう"世界"がなくてはならないのでしょう。そういうことを感じ取れる感覚が、この私に育っているかどうかの問題なのです。
この頃は、小学校、幼稚園、そして保育園でも英語の学習が取り入れられているようです。
ある日の孫(幼稚園年長組女の子)と私の会話。
「おじいちゃん、リンゴのこと英語でなんて言うか知ってる?」
「知ってるよ、"アップル"でしょう」
「ちがうちがう、"アポー"(発音どおりに書けません)だよ!」
「おじいちゃん、英語で"いただきます"ってどう言うの?」
「ん、………?」
英語のことはよくわからないのですが、多分「いただきます」ということばはないのでは、と思うのですがどうでしょうか。
日本には「いただきます、ごちそうさま、有難うございます、もったいない、お大事に、申し訳ありません、ごめんなさい、お恥ずかしい(ことです)」などという独特のことばがあります。
天地自然のはたらきを身に受けて、あらゆる生命(いのち)と共に生きていることを深い感動をもって受け止める、「いただく」「もったいない」「有難(ありがた)し(有ること難(かた)し)」などという言語表現は、日本人以外には無いのではないかと思うのです。
「私たちがものを考えたり行動したりする本(もと)となるのは、その人が積み重ねてきた生活習慣にある」といわれています。
どのような環境に生まれ、どのような育成を受け、どのような習慣を身につけたかが、その人の言動の本(もと)になるということでしょう。それほど日常の生活習慣は大きな意味を持つということなのだと思います。
人と人とを結び付ける大事なはたらきをする「ことば」を通して、私たちの感覚を育ててきた日本という国が、他の国に例を見ない独特の文化を築いてきたことを、いま改めて思い起こしていきたいと考えています。
第三十ニ回
2021-02-03
昨年秋から増え始めた新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。そのような中、11都道府県を対象にした二度目の緊急事態宣言が発令されました。
私たちの身の回りでも、いつの間にか感染者が増加し、それこそ"人ごとではない"状況になってしまいました。
新しい生活様式ということでさまざまな方法がとられ、何とかこの状況を乗り切ろうと懸命の努力が続けられていますが、私たちの生活に及ぼす影響は計り知れないものがあります。
先日気になる新聞記事が目に留まりました。このコロナ下の暮らしの変化の一つとして、自殺者の増加ということが報じられていたことです。
中でも、女性の自殺者が二年ぶりに増加したことが挙げられ、その原因がコロナの流行に伴う経済情勢の悪化や、外出自粛などで外出の機会が減り、子育てや介護、家庭内暴力などに関わる問題が深刻化したことにあると分析していました。
私たちの身の回りでも、いつの間にか感染者が増加し、それこそ"人ごとではない"状況になってしまいました。
新しい生活様式ということでさまざまな方法がとられ、何とかこの状況を乗り切ろうと懸命の努力が続けられていますが、私たちの生活に及ぼす影響は計り知れないものがあります。
先日気になる新聞記事が目に留まりました。このコロナ下の暮らしの変化の一つとして、自殺者の増加ということが報じられていたことです。
中でも、女性の自殺者が二年ぶりに増加したことが挙げられ、その原因がコロナの流行に伴う経済情勢の悪化や、外出自粛などで外出の機会が減り、子育てや介護、家庭内暴力などに関わる問題が深刻化したことにあると分析していました。
もう一つは、ジャーナリストの池上 彰さんの文章です。
ー感染を防ぐには、「ソーシャルディスタンスをとることが必要だ」と言われるようになりました。でも
ー感染を防ぐには、「ソーシャルディスタンスをとることが必要だ」と言われるようになりました。でも
ソーシャルディスタンスは「社会的距離」という意味です。私たち人間は、社会の中でこそ生きていけ
るもの。他人との間に「社会的距離」を取っていては、寂(さび)しくて辛(つら)いのです。ここは
「フィジカルディスタンス(物理的距離)」という言葉を使うようにしましょう。物理的距離は離れて
いても、社会的距離つまり「心の距離」は離れない。そんな生き方を心がけようではありませんか 一
誠にその通りだなと感心させられました。意味もわからず「ソーシャルディスタンス」などと言っていたことが恥ずかしくなりました。
人間は近年ことに個人主義的傾向が強くなったように感じられます。自分さえよければ、自分に害がおよばなければ何をしても、何を言ってもかまわない。それによって他人がどうなろうと意に介さない。そんな気分が広がっているような気がしてなりません。
この不自由な生活の中でも、私たちは「人間(じんかん)」一間柄を生きる存在、人と人、ものと人との関わり合いを生きる関係的存在一であることを肝に銘じて、「心の距離」を離れずに生きて往(ゆ)きたいものです。
人間は近年ことに個人主義的傾向が強くなったように感じられます。自分さえよければ、自分に害がおよばなければ何をしても、何を言ってもかまわない。それによって他人がどうなろうと意に介さない。そんな気分が広がっているような気がしてなりません。
この不自由な生活の中でも、私たちは「人間(じんかん)」一間柄を生きる存在、人と人、ものと人との関わり合いを生きる関係的存在一であることを肝に銘じて、「心の距離」を離れずに生きて往(ゆ)きたいものです。
第三十一回 新年ご挨拶
2021-01-08
新年明けましておめでとうございます。
皆様方には、令和三年の新春をどのように迎えられたでしょうか。
昨年はコロナに明けコロナに暮れた一年間でしたが、厳しく辛い日々を過ごされた方も多かったのではないかと存じます。影響を受けられた方々には心よりお見舞いを申し上げます。
会津地方は、当初少ない感染者数を維持(いじ)してきましたが、いつの間にか数が増え、いよいよ身近に迫ってきたことをひしひしと感じさせられています。
幸いにも当社協におきましては、変わらぬ市民の皆様の温かいご支援に支えられ、ここまで自粛(じしゅく)を余儀(よぎ)なくされつつも、できる限りの事業に取り組んでまいりました。おかげ様で職員一丸となっての感染予防対策のもと、ご利用いただいている方々、職員一同感染者を出すことなく過ごせましたこと、改めて感謝申し上げる次第でございます。
今年もまた、感染予防対策怠りなく、可能な限り事業を実施して参りますので、皆様方の一層のご理解とご支援を賜わりますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
「新しい生活様式」といわれるように、私たちの生活は今までとは大きく変わりました。
マスクをつけ、密(みつ)を避けての生活は、本来の人と人との触れ合いの場を奪ってしまいました。マスク越しの応対(おうたい)は、表情を通しての互いの感情の確かめ合いが不十分となり、特に子供と母親や保育園・幼稚園・学校の先生との間で、大事な「笑顔」が伝わりにくくなったことが心配されているようです。
不自由な生活の中で、不安と閉塞感(へいそくかん)とやり場のないイライラに覆(おお)われて、他人に不必要に当たり散らすという行為が増えてきました。
私たちが、このコロナ禍の中で経済的に失うものが多いこともありますが、人間性を見失っていくことの恐ろしさも実感させられています。
今や全人類が未曾有(みぞう)の出来事に直面し、私たち一人一人の上にその対応(たいおう)が求められている、「時」を生きなければならないのだと感じさせられています。
今年一年を通してこの難しい課題をしっかり受け止め、克服していくために力を合わせ、平穏な生活に戻れるよう収束に向けて歩んでまいりたいと思います。
皆様方には、令和三年の新春をどのように迎えられたでしょうか。
昨年はコロナに明けコロナに暮れた一年間でしたが、厳しく辛い日々を過ごされた方も多かったのではないかと存じます。影響を受けられた方々には心よりお見舞いを申し上げます。
会津地方は、当初少ない感染者数を維持(いじ)してきましたが、いつの間にか数が増え、いよいよ身近に迫ってきたことをひしひしと感じさせられています。
幸いにも当社協におきましては、変わらぬ市民の皆様の温かいご支援に支えられ、ここまで自粛(じしゅく)を余儀(よぎ)なくされつつも、できる限りの事業に取り組んでまいりました。おかげ様で職員一丸となっての感染予防対策のもと、ご利用いただいている方々、職員一同感染者を出すことなく過ごせましたこと、改めて感謝申し上げる次第でございます。
今年もまた、感染予防対策怠りなく、可能な限り事業を実施して参りますので、皆様方の一層のご理解とご支援を賜わりますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
「新しい生活様式」といわれるように、私たちの生活は今までとは大きく変わりました。
マスクをつけ、密(みつ)を避けての生活は、本来の人と人との触れ合いの場を奪ってしまいました。マスク越しの応対(おうたい)は、表情を通しての互いの感情の確かめ合いが不十分となり、特に子供と母親や保育園・幼稚園・学校の先生との間で、大事な「笑顔」が伝わりにくくなったことが心配されているようです。
不自由な生活の中で、不安と閉塞感(へいそくかん)とやり場のないイライラに覆(おお)われて、他人に不必要に当たり散らすという行為が増えてきました。
私たちが、このコロナ禍の中で経済的に失うものが多いこともありますが、人間性を見失っていくことの恐ろしさも実感させられています。
今や全人類が未曾有(みぞう)の出来事に直面し、私たち一人一人の上にその対応(たいおう)が求められている、「時」を生きなければならないのだと感じさせられています。
今年一年を通してこの難しい課題をしっかり受け止め、克服していくために力を合わせ、平穏な生活に戻れるよう収束に向けて歩んでまいりたいと思います。