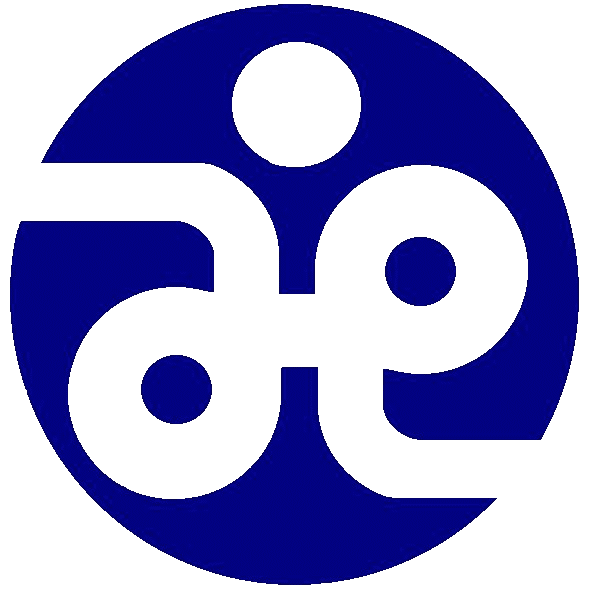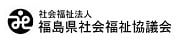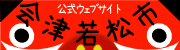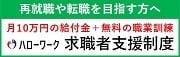会長のつぶやき
会長 武藤淳一
【生年月日】1942年(昭和17年)6月15日
【住まい】福島県会津若松市
【家族構成】妻、長男夫婦、孫2人の6人家族
【本職】寺院住職
【経歴】大学卒業後、教職を経て住職に。PTA役員、民生児童委員等を経験。
【住職として伝えたいこと】
「家庭」「生活」―人間として何をすること(ところ)なのかを学び実践すること
【仕事をする上で気をつけていること】丁寧(心を込めて親切に対応すること)
【座右の銘】身自當之しんじとうし無有代者むうだいしゃ(仏教の言葉)
意味:人生の中で苦しいこと、悲しいことに出会っても、誰も代わってくれないし自ら引き受けて生きていく
【尊敬する人】親鸞
【最近読んだ本】天地明察
第六十回
2023-07-07
人口の増加が報ぜられる国がある一方で、世界有数の豊かな国である日本では、子供の数が減り続け、人口減少が心配されています。
私たちは、今日まで国を挙(あ)げて豊かさを求め走り続けてきました。そして日本中の都市化を目指し、個々人がそれぞれ自分の都合に合う環境条件を整えることで、そのことを実現させようとしてきました。その結果として「家庭」や「家族」の形態や考え方が大きく変化してきました。
昭和の初め頃はまだ珍しかった、サラリーマンと呼ばれる人が増え続け、男性は外で仕事、女性は専業(家事、育児)主婦ということが社会の「常識」のように考えられ、夫婦中心の核家族が一般的になりました。
それによって経済の成長は遂(と)げてきましたが、「人間の成長」ということに関して言えば、家庭や地域の教育力を低下させてきたように思います。
出産・育児・家庭教育・杜会教育が、極めてプライベートな問題(個人の都合に左右される)になってしまいました。祖父母でさえ関わりが少ない、そういう環境に子供が置かれています。
考えてみれば、女性にとって出産・育児は、生まれて初めての経験ですから不安を抱えるのは当然です。子供を育てるという大事業が、母親一人の手だけでできることではありません。その不安を、与えすぎやワガママ容認(ようにん)や過保護で対応してしまうと、子供の健全な成長は損(そこ)なわれがちになります。
基本的に出産・育児は、本来個人的に密室で行われるようなものではなく、パブリック(公)なことではないかと思います。関係するすべての人々が、その子の安全や成長に関心を払い、できる範囲でお手伝いをするという、かつてはどこにでもあった伝統的風景のように思います。
生まれた子供が、親の思い通りになるなどあり得ないことです。その不如意(ふにょい)(思い通りにならない)を経験しながら、親も子もともに「人間」になっていくのでしょう。子供が人間であるという事実と真正面からぶつかることが、親に人間であることを迫(せま)る。そうして子供が育つことを通して、家族やその周囲が絆を深め、大切にし合う関係を築きながら、社会が形成され維持(いじ)されていたのでしょう。それが、都市化・個別化の中で崩(くず)れてきたのが、今の社会の状況となっているのではないかと思われます。
少なくとも、個別に都合が満たされるほど価値があるという見方考え方を方向転換しない限り、少子化に歯止めがかからず、若い人たちの犯罪(罪の意識が希薄(きはく)で、本当に気軽(きがる)に行っているようにしか見えない)も減らないのではないかと思います。
第五十九回
2023-05-25
先日読んだ本の一節を引用させていただきます。
「かれは、われを罵(ののし)った、かれは、わたしを害した。かれは、われにうち勝った。(中略)」という思いをいだく人には、怨(うら)みはついに息(や)むことがない。(『法句経(ほっくきょう)』三 中村元訳)
実にこの世において、怨みに報(むく)いるに怨みを以(もっ)てしたならば、ついに怨みの息むことがない。怨みをすててこそ息む。これは永遠の真理である。(同上)
2001年9月11日、アメリカ・ニューヨークの「世界貿易センター」に、ハイジャックした旅客機を衝突(しょうとつ)させるという衝撃(しょうげき)的な事件が起こりました。それはちょうど私が私学視察でアメリカに到着した翌朝のことでした。その訪問先であるクロスロード・スクールの理事長ポール・カミンズ先生は、ブッシュ大統領の声明の翌日に、「大統領の声明はWho (犯人)とHow(方法や程度)のみで、もっとも大事なWhy(原因や経緯)への言及がない。また自らを正義・善とし、それを攻撃するものを悪魔だと断定しているがいかがなものか」と、私たちにおっしやいました。テロ直後で、全米が興奮気味に報復(ほうふく)だ、戦争だと声高(こわだか)に叫んでいる時にです。
その識見(しっけん)と勇気にふれ、いろいろと考えずにはいられませんでした。アメリカを中心とする「世界」と、大地から汗を流して生産するところから一番遠いところで巨額のマネートレードが行われる「貿易」、そして自分たちこそが「センター」であるという、その「世界貿易センター」がテロ攻撃を受けて崩壊しました。テロが卑劣(ひれつ)で一片(いっぺん)の擁護(ようご)の余地(よち)もない行為であることは言うまでもありませんが、そこに何かしら新世紀の私たちの進む方向の大きな欠陥(けっかん)や思い上がりを思い知らされたように感じます。
仏教では、人間は「三毒(さんどく)の煩悩(ぼんのう)(貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)・愚痴(ぐち))」を持つと教えられています。
貪欲・・・自分中心の果てしのない、満足を知らない欲望充足(じゅうそく)活動
瞋恚・・・いつも他と比べて勝ちを目指し、負けて怒(いか)り、思い通りにならなくて憎(にく)む
愚痴・・・そういう自己の事実にまったく目を向けず、自覚することもなく、いつも自分の都合という物差(ものさし)で考え行動する
私たちの無自覚さの上に成り立っている文明そのものといえるようです。
そのことと同時に思われることは、先の世界貿易センターに象徴される今の私たちの世界に、「畏敬(いけい)」の心が見失われているということです。
自然を畏(おそ)れ自然を敬(うやま)う。人間を畏れ人間を敬う。人知(じんち)を超(こ)えたものを、人間を含めたすべての存在を支えている一切のものを畏れ敬う。
「畏れる」とは、その価値や力、偉大(いだい)なはたらきを認め、謙虚(けんきょ)になるということです。「敬う」も、意味や価値を理解し、尊び、丁寧に心を込めて対処するということです。自らの限界を知り、また自らを支える願いやはたらきの無限性を知ることです。
「われらは、ここにあって死ぬはずのものである。」と覚悟をしよう。一このことわりを他の人は知っていない。しかし、このことわりを知る人々があれば、争いはしずまる。(『法句経(ほっくきょう)』中村元訳)
死すべき人間同士が、不可思議(ふかしぎ)の力に生かされて今ともに生きている。その事実からすべてが始まると知らねばならない。
第五十八回
2023-04-21
最近立て続けに、年齢も近く、懇意にしていた方の葬儀に接する機会があり、「死」というものがより身近に感じられるようになりました。自分の年齢と重ね合わせて、改めて自分の人生や死のことを我が事として考えさせられています。
「われらは、ここにあって死ぬはずのものである。」と覚悟をしよう。ーこのことわりを他の人は知っていない。しかし、このことわりを知る人々があれば、争いはしずまる。(『法句経』(ほっくきょう)中村元訳)
私たちは、生きているのが素晴らしいと考えるあまり、死の意味を見逃してしまいがちです。「生きているときが花で、死んだらお終(しま)い」というような言葉も耳にします。現代人の死生観は、生のみの人生観になっているようです。それは、物事を自分にとって都合のいい面だけ見ていこうという姿勢で、いわば紙の表だけを求めようとするようなものです。
私たちが「人生」と呼んでいるものを仏教では「生死(しょうじ)」と表現します。それは生と死を併存(へいぞん)した人生観です。西洋でも「人間は死に向かって生きているものである」(ハイデッカー・哲学者)と言われるように、死を視野に入れて生を考えるのは当然のことであり、健康な人生観であるといえます。
言うまでもなく、どの人も皆死ぬ人です。例外はありません。絶対的真実といえるでしょう。人間は逞(たくま)しいものですが、またはかなく脆(もろ)いものです。そして自分自身のいのちがいつまで続くのか、いつどのような形で終わるのか、全く知り得ません。また計画することもできません。死ぬ者同士の私たちであると分かったとき、私たちが為すべきことは、支え合い、生かし合うことことのみでしょう。
心電図をとった方から聞いたことがあります。一日に10万回余の鼓動が記録されていたそうです。心臓が止まったら死ぬ私のその心臓は、今日までずっと動き続けて、私を生かしてきてくれました。眠っているときも働いているときも、気分のいい時も落ち込んでいるときも……。
「メメント・モリ」(死を想えと訳されていました)という言葉を聞いたことがあります。仏教的には「念死(ねんし)」(常に死から目を逸(そ)らすな)ということで、そのことがすなわち生を見つめることになるということです。
死の意味や人生における位置が明らかになると、生きている今の意味や価値も見えてきます。思い通りに生きることにのみ価値を見ようとする私たちには、老・病・死は「苦」ですが、死を見つめることで、私が私という人間として生まれ、亡き人も含め数多くの方々との関係の中で生きてきたことの自覚が生まれ、そこから満足や喜びが見出せるのではないかと思います。目を逸らし、老病死から逃げ回るような人生は、むしろ「生」がはっきりしません。死をごまかすと、生も実感できなくなるのです。
私たちは、身近な人の死に出会うと辛(つら)く悲しい思いを持ちますが、同時にその死を通してその人の生、つまりその日まで生きておられたここに一つの尊い人生があったということが、くっきりとしてきます。そこから、この私の人生も尊いものであったと、だから大事に丁寧(ていねい)に生きて、決して空(むな)しく過ごすようなことのないよう生きなければならないと知らされ、生きる楽しさや喜びも素直に感じられるのでしよう。
老病死をはじめ、イヤなことから目を逸(そ)らし避(さ)けようと、逃げ回っているだけが私の人生の姿となっていないか、問うていかねばならないと感じさせられています。
第五十七回
2023-03-16
「震災と戦争とはよく似ています」。1月に93歳で亡くなった作家で精神科医の加賀乙彦さんが「自伝」に記している。「どちらにおいても人間は自分の生きる場を奪われ、故郷を奪われ、ものもなくなり、当(あ)て所(ど)なくさまよい歩くしかない」。▲ロシアのウクライナ侵攻、トルコ・シリア大地震で苦しむ人々も同じだろう。10年以上内戦が続くシリアでは二つの苦しみがのしかかる。第二の都市アレッポでビルが倒壊し、lO人以上が亡くなったのは地震のl5日前だった。▲一時、反政府軍の拠点(きょてん)になり、激しい爆撃を受けた。多くの建物が損傷し、倒壊の危機性があったといわれる。そこに巨大地震だ。トルコ側に逃(のが)れた数百万のシリア難民も直撃を受けた。▲きようは東京大空襲から78年。あすは東日本大震災から12年を迎える。原発事故も戦争と同様に大災害級の被害をもたらす人災である。福島の人たちも二重の苦しみにさいなまれてきた。(以下中略)人々の痛みに思いをはせ、支援を続けたい。(3月10日付毎日新聞「余禄」掲載文)
私たちの周りの常識的な感覚として、他人に何かをしてもらうことは精神的負担であり、それにふさわしい何か(お礼など)で清算(せいさん)してバランスをとりたくなります。そのお返しが煩(わずら)わしいからと、困っていても他人に助けてもらうのをためらうことも少なくありません。
背の高い人は上の物をとるのに都合がよく、低い人は下の作業がしやすい、それだけのことです。そこに優劣も強弱もありません。みなできることとできないことのある者同士です。だから「お互いさま」と助け合う。「平等」とは、努力して勝ち取るものと思っていたら、それは自分の不完全さに気付き、そういう自分を引き受けてみると、既(すで)に開かれている世界でした。私たちは、本来平等であったのを、強がりと見栄(みえ)と浅知恵(あさぢえ)などで、差別の世界にしていたのです。大切なことは、自分のできることは惜しまずやり、できないことは、悩んだり気遣(きづかい)いし過ぎずにお願いすることです。
住む人が少なくなった状態を「過疎(かそ)」といいますが、周りに多くの人がいても、挨拶や言葉の交(か)わし合いがなくなれば、それが過疎(孤立化)となります。隣人を信じて安心して頼り合い、明るく豊かな共生を実現することが過疎の解消につながります。そしてそのことが私自身の生きている意味や価値を再確認する大切な場であると、喜びを得ながらコミュニケーションを回復していくことが大切なことだと思います。
本来ボランティアとは、無償(むしょう)の行為ということではなく、「自発的行為」という意味だと聞いたことがあります。
大切なのは、私たち自身の自発性や、「互いに、共に」という意識や意欲なのでしょう。互いにあらゆる人と関係し合いながら生きている私たちが、「人間」であり続けるために世話し合い、世話され合うという相互性が大事です。
「誰にも迷惑かけずに」といいますが、地球環境から言えば、人間が存在していることそのものが大変な迷惑なのです。公共のルールを守らないなどは論外ですが、問題は、迷惑をかけ続けて生きざるを得ない自分の「自覚」なのです。直接間接を問わず、世話になり合う安心感や信頼、相互敬愛(そうごけいあい)の豊かさを知り、互いにできることをし合いましょう。まず「ありがとう」の交換から始めましょう。
第五十六回
2023-02-15
最近の新聞、テレビのニュースを見ていると、耳を疑いたくなるような事件が、しかも頻繁(ひんぱん)に起こっていることが報じられ、驚かされています。強盗、殺人、詐欺(さぎ)、子供までがターゲットにされる性犯罪、飲食店での信じられないような迷惑行為、宗教(?)団体による詐欺まがいの事件、五輪開催における利権がらみの問題、政治家の行動や問題発言など枚挙(まいきょ)にいとまがないほどです。いったいこの国の人間は、どうなってしまったのだろうかと、呆(あき)れると同時に心配になってしまいます。
この頃気になることの一つに、この国における「私と公(わたくしとおおやけ)」のことがあります。そのけじめというか境界が崩壊(ほうかい)もしくは意識から抜け落ちているような印象を持ちます。世界中どこでも個人として確保されるべきことと、公共・共有の物として大事にされるものと、どちらもきちんと教えられています。
「私」としては許されるが、「公」の場では控えるべきこと、「私」としては控えても、「公」としては積極的になるべきこと等それぞれあります。誰か(私的)の大きな声を公と見誤ってはなりません。
日本の「公」は「おおやけ」すなわち「大きな家」(有力者、権力者)をさす言葉から始まったからでしょうか。公といえば上から与えられる「官(かん)」のイメージが強くあり、公(こう)と官とが混同されるきらいがあります。しかし欧米における「公(パブリック)」は「民(みん)」によって形成されてきました(イギリスではパブリック・スクールの語で、私立中学校を意味するそうです)。そのせいかどうかわかりませんが、日本では「公衆○○」などの公的な場所をきれいに使おうという意識が薄いようです。
「公」は本来「開かれた共なる場」のことで、私有(しゆう)してはならないものでしょう。そこには必ずルールがあり、公を形成する人たちの意識が求められます。そのルールは官から与えられるものではなく、私とあなたと共に生きるもの(民)が、作っていくものです。
私は単独では誕生も生存もできないもので、あらゆる関係性の中に存在しています。私は、私に委(ゆだ)ねられた人生の当事者・主体であると同時に、時間空間を共にするあらゆるいのちとの連帯の中に位置づけられています。私という存在には、私有できない公的(こうてき)意味(公(おおやけ)性)ということがあるのです。その公が公として尊重され維持されることで「私」が豊かになっていきます。
教育は、人間が人間になるためにどうしても必要なもので、それは人間の手によってなされねばなりません。少なくとも「学校」というものは、民のために、民によってつくられ、民によって運営されている公(こう)教育機関です。あらゆる施設・物品は、私たちが共有する大切なものです。私たち一人一人がよく考えて、丁寧(ていねい)に維持(いじ)していかなければなりません。公をつくり公を尊重するという意識で、公的状況へ出ていきましょう。そこで他者と出会い、そして自分に出会う。そここそが、あなたと私の生きる場なのでしょう。
この頃気になることの一つに、この国における「私と公(わたくしとおおやけ)」のことがあります。そのけじめというか境界が崩壊(ほうかい)もしくは意識から抜け落ちているような印象を持ちます。世界中どこでも個人として確保されるべきことと、公共・共有の物として大事にされるものと、どちらもきちんと教えられています。
「私」としては許されるが、「公」の場では控えるべきこと、「私」としては控えても、「公」としては積極的になるべきこと等それぞれあります。誰か(私的)の大きな声を公と見誤ってはなりません。
日本の「公」は「おおやけ」すなわち「大きな家」(有力者、権力者)をさす言葉から始まったからでしょうか。公といえば上から与えられる「官(かん)」のイメージが強くあり、公(こう)と官とが混同されるきらいがあります。しかし欧米における「公(パブリック)」は「民(みん)」によって形成されてきました(イギリスではパブリック・スクールの語で、私立中学校を意味するそうです)。そのせいかどうかわかりませんが、日本では「公衆○○」などの公的な場所をきれいに使おうという意識が薄いようです。
「公」は本来「開かれた共なる場」のことで、私有(しゆう)してはならないものでしょう。そこには必ずルールがあり、公を形成する人たちの意識が求められます。そのルールは官から与えられるものではなく、私とあなたと共に生きるもの(民)が、作っていくものです。
私は単独では誕生も生存もできないもので、あらゆる関係性の中に存在しています。私は、私に委(ゆだ)ねられた人生の当事者・主体であると同時に、時間空間を共にするあらゆるいのちとの連帯の中に位置づけられています。私という存在には、私有できない公的(こうてき)意味(公(おおやけ)性)ということがあるのです。その公が公として尊重され維持されることで「私」が豊かになっていきます。
教育は、人間が人間になるためにどうしても必要なもので、それは人間の手によってなされねばなりません。少なくとも「学校」というものは、民のために、民によってつくられ、民によって運営されている公(こう)教育機関です。あらゆる施設・物品は、私たちが共有する大切なものです。私たち一人一人がよく考えて、丁寧(ていねい)に維持(いじ)していかなければなりません。公をつくり公を尊重するという意識で、公的状況へ出ていきましょう。そこで他者と出会い、そして自分に出会う。そここそが、あなたと私の生きる場なのでしょう。