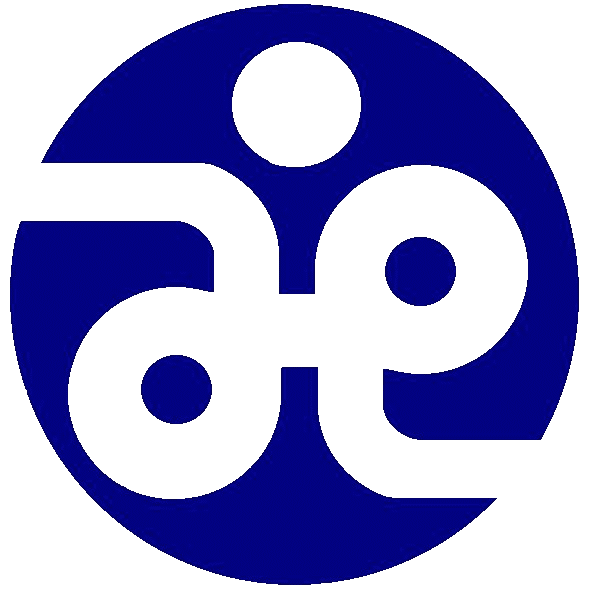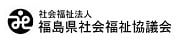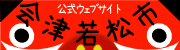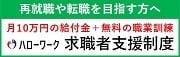会長のつぶやき
会長 武藤淳一
【生年月日】1942年(昭和17年)6月15日
【住まい】福島県会津若松市
【家族構成】妻、長男夫婦、孫2人の6人家族
【本職】寺院住職
【経歴】大学卒業後、教職を経て住職に。PTA役員、民生児童委員等を経験。
【住職として伝えたいこと】
「家庭」「生活」―人間として何をすること(ところ)なのかを学び実践すること
【仕事をする上で気をつけていること】丁寧(心を込めて親切に対応すること)
【座右の銘】身自當之しんじとうし無有代者むうだいしゃ(仏教の言葉)
意味:人生の中で苦しいこと、悲しいことに出会っても、誰も代わってくれないし自ら引き受けて生きていく
【尊敬する人】親鸞
【最近読んだ本】天地明察
第五十五回(年頭挨拶)
2023-01-06
新年明けましておめでとうございます。
令和五年の新春を寿(ことほ)ぎ、市民の皆様方の昨年中にお寄せいただきましたご厚情に対しまして心より御礼申し上げますとともに、今年一年が希望(癸卯一干支(えと)で「みずのとう」、音読みで「きぼう」)に満ちた年であってほしいと願っております。
今、私たちを脅(おびや)かし続けているコロナ感染、世界の国と国との紛争、物価の高騰(こうとう)、地球温暖化による気候変動などが一日も早く終息、解決の方向に向かい、すべての人々が安心して暮らせる日々を取り戻すために、何ができるのかを考えていかなければならないと、思いを新たにしております。
私ども社会福祉協議会では、地域福祉活動計画の理念であります「誰もが安心して暮らせるよう、地域で支え合うあいづわかまつ」を目指して、各種事業を展開しています。
しかしながら、近年とみに地域社会を取り巻く環境の変化により、地域での支え合いの機能が弱まり、地域住民が抱える生活課題が深刻化しております。
中でも、少子高齢化の進行により当市の人口減少が進み、このままいけば十数年後には10万人を切るのではないかと危ぶまれています。また、さらに心配されるのは、高齢者の数に比して子供の人口滅少が著しいことです。未婚率の高さ(30〜34歳の男性46.4%、女性31.5%(令和2年国勢調査より))とそれに伴う出生率の低下が顕著に表れています。
子供、高齢者、障がい者などすべての人々が、地域で暮らし生きがいを共に創ることのできる「地域共生社会」の実現に向け、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、行攻の公的制度に頼るだけではなく、住民手作りの福祉活動を根付かせていくことが求められています。
そのためには欠かせない組織となる、身近な住民同士が連携しお互いに助け合い支え合う、活動展開の役割を担う「地区社協」の設立に取り組んでまいりました。
おかげさまで、先に設立された五つの地区に加え昨年は、大戸地区、城西地区、日新地区においても設立されましたことは、地区の皆様のご理解とご尽力の賜と心より敬意と感謝を申し上げるところであります。
この組織は、地域と社会福祉協議会を繋ぐ大事な基盤であります。本会としましても出来うる限りの支援をしてまいりたいと思いますので、今後の活動に大きな期待を寄せるところであります。
今年もコロナ感染予防に努めながらの事業展開となりそうですが、職員一丸となって力を尽くしていく所存ですので、市民の皆様にはより一層のご支援をいただきますようよろしくお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。
第五十四回
2022-11-30
先日、久々に壮大(そうだい)な天体ショーを見させてもらいました。月と地球と太陽が一直線に並び、しかも天王星が月の裏側にかくれ(これは見えませんでした)たり、月が地球の影に入って色や形が変化するさまを、寒さも忘れてしばし見とれてしまいました。
私の誘いに応えて、二人の孫とそれにつられて両親が外に出てきてくれて、いっしょに至福(しふく)の時を過ごしました。次は400年後に起きるそうなので、また一緒に見ようね(?)などと言いながら部屋に戻りました。
悲しいことは、誰かに"悲しいでしょう"と言ってもらわなくても、何とか一人で悲しみに耐えられますが、うれしいことは、そばで共に喜んでもらわないと、うれしさが消えてしまうという性質のもののようです。
この天体ショーも、外に誘った孫たちが一緒になって"ワー!すごい、きれいだね一"と言ってくれると美しさも喜びも二倍三倍に膨(ふく)らんでくれます。逆に"フーン、さむい"と言ってさっさと部屋に戻ってしまったら、美しさもうれしさも消し飛んでしまうのではないかと思います。
「心の貯金をすると 笑顔の利子がつく」(あるお寺の掲示板の言葉)。心が豊かになると、笑顔で言葉や挨拶のやり取りができる幸せを享受(きょうじゅ)できるということでしょう。
かつての日本の一つの風景に、老人と子供たちが触れ合っている姿があったように思います。子供と遊ぶ良寛(りょうかん)さまのように、各家に孫の相手をしている老人の笑顔が、不思議と双方の波長が合っていたように思います。そういう姿を見ることが少ないのは何故でしょうか。核家族や少子化というだけではないような気がします。
豊かな「もの」を感じる中で、先程の老人と子供について思い当たったことは、本来、子供も老人も経済優先というか損得(そんとく)で動くものではないということです。だからこそ、老人が地域で尊敬され、子供が地域の宝として大事にされたのでしよう。少なくとも子供たちは、童話「裸の王様」に示されるように、金や力に振り回されない世界に生きているのです。
私たちが求める幸せの大きな要素は、お金と力と健康に集約(しゅうやく)されると思われています。しかし、その金と力とは違う次元の幸せがあるということが、加齢(かれい)とともに見えてきます。お金があっても力があっても不幸であることは少なくないことを経験します。
かつて不幸とは「貧・病・争」、つまり貧困(ひんこん)や傷病(しょうびょう)や人間関係のトラブルにあるといわれ、また犯罪の温床(おんしょう)は貧困と考えられていました。
私の誘いに応えて、二人の孫とそれにつられて両親が外に出てきてくれて、いっしょに至福(しふく)の時を過ごしました。次は400年後に起きるそうなので、また一緒に見ようね(?)などと言いながら部屋に戻りました。
悲しいことは、誰かに"悲しいでしょう"と言ってもらわなくても、何とか一人で悲しみに耐えられますが、うれしいことは、そばで共に喜んでもらわないと、うれしさが消えてしまうという性質のもののようです。
この天体ショーも、外に誘った孫たちが一緒になって"ワー!すごい、きれいだね一"と言ってくれると美しさも喜びも二倍三倍に膨(ふく)らんでくれます。逆に"フーン、さむい"と言ってさっさと部屋に戻ってしまったら、美しさもうれしさも消し飛んでしまうのではないかと思います。
「心の貯金をすると 笑顔の利子がつく」(あるお寺の掲示板の言葉)。心が豊かになると、笑顔で言葉や挨拶のやり取りができる幸せを享受(きょうじゅ)できるということでしょう。
かつての日本の一つの風景に、老人と子供たちが触れ合っている姿があったように思います。子供と遊ぶ良寛(りょうかん)さまのように、各家に孫の相手をしている老人の笑顔が、不思議と双方の波長が合っていたように思います。そういう姿を見ることが少ないのは何故でしょうか。核家族や少子化というだけではないような気がします。
豊かな「もの」を感じる中で、先程の老人と子供について思い当たったことは、本来、子供も老人も経済優先というか損得(そんとく)で動くものではないということです。だからこそ、老人が地域で尊敬され、子供が地域の宝として大事にされたのでしよう。少なくとも子供たちは、童話「裸の王様」に示されるように、金や力に振り回されない世界に生きているのです。
私たちが求める幸せの大きな要素は、お金と力と健康に集約(しゅうやく)されると思われています。しかし、その金と力とは違う次元の幸せがあるということが、加齢(かれい)とともに見えてきます。お金があっても力があっても不幸であることは少なくないことを経験します。
かつて不幸とは「貧・病・争」、つまり貧困(ひんこん)や傷病(しょうびょう)や人間関係のトラブルにあるといわれ、また犯罪の温床(おんしょう)は貧困と考えられていました。
しかし、今経済的には豊かで健康で家庭環境に恵まれているとみられる子供たちが、心の中に大きな問題を抱えているようです。今の状況を見ると、自己の内的空白(ないてきくうはく)というか「透明(とうめい)な存在」という言葉に代表される存在感の希薄(きはく)さ、生きるリアリティ(現実感・生活実感・手応え)が感じられないこと、また周りとの関係が結べない、居場所がないというようなことが、子供にとって、いや大人にとっても、何か(反社会的なことも含めて)せずにいられない程の轡積(うっせき)となっているようです。
「おじちゃん、おはよう。風邪(かぜ)よくなった。大事にしてね。」
「おはよう、○○ちゃん。まだ少し咳(せき)が出るけどおかげでだいぶよくなったよ。有難う。」
と、笑顔であいさつできる幸せをかみしめましょう。そして笑顔で言葉を交わし合う人間の中に生きている幸せを大事にしたいものだと思います。
「おじちゃん、おはよう。風邪(かぜ)よくなった。大事にしてね。」
「おはよう、○○ちゃん。まだ少し咳(せき)が出るけどおかげでだいぶよくなったよ。有難う。」
と、笑顔であいさつできる幸せをかみしめましょう。そして笑顔で言葉を交わし合う人間の中に生きている幸せを大事にしたいものだと思います。
第五十三回
2022-11-02
先日、新入職員の歓迎の意味を込めた、昼食会を催(もよお)していただきました。コロナ感染の蔓延(まんえん)以来、全職員での歓送迎会を開げずにいることから、いつも幹事役を担(にな)っていいただいている職員さんの発案で、楽しい昼食の時間を用意していただきました。もちろん大勢参加の会食はできませんので、幹事さんの独断と偏見により厳選された(?)数名の職員での昼食会でした。和気(わき)あいあいとした雰囲気(ふんいき)の中で、おいしい昼食をご馳走(ちそう)になりました。
「食」とは、私たちのいのちと身心を養い育てて、保ち続けるものです。それぞれの「食」、が咀噌(そしゃく)され消化吸収されて、私の体といのちの一部になります。
「食」とは、私たちのいのちと身心を養い育てて、保ち続けるものです。それぞれの「食」、が咀噌(そしゃく)され消化吸収されて、私の体といのちの一部になります。
私たちが、人間として育ち成長していくのに何が必要でしょうか。口から入る食物のみではありません。知識・知恵・経験・情報、さまざまなモノ、また親や友人をはじめとする種々の人間関係(ふれあい)や思い出も大切です。そして、願われてある存在(いのち)であることに気づくことが、安心や元気につながります。
仏教では、私たちの生命維持(いじ)と成長に必要な、四つの「食」を教えています。これを「四食(しじき)」といいます。
仏教では、私たちの生命維持(いじ)と成長に必要な、四つの「食」を教えています。これを「四食(しじき)」といいます。
1、段食(だんじき) 一 一口一口の日々の飲食物のこと。肉や野菜などの実際の食物をいう。
2、触食(そくじき) 一 外界(げかい) とのとの接触(せっしょく)のこと。親鳥が卵を温かく抱くことで
2、触食(そくじき) 一 外界(げかい) とのとの接触(せっしょく)のこと。親鳥が卵を温かく抱くことで
雛(ひな)が孵化(ふか)し育つように、いのちあるものは温かい触れ合いによっ
て育ちます。
私たちは、よき人と、自然と、動植物などとの触れ合いに育てられています。
3、思食(しじき) 一 自分の意志や思考が身体や生命を養うということ。自分の成りたい状態を願い求
私たちは、よき人と、自然と、動植物などとの触れ合いに育てられています。
3、思食(しじき) 一 自分の意志や思考が身体や生命を養うということ。自分の成りたい状態を願い求
め、その意欲をもって自分を育てよう高めようという意思が、その人を育てると
いうこと。
4、識食(しきじき) 一 精神の主体(心)をいう。見たもの、聞いたこと、香り、味、感触とその内容を認識
4、識食(しきじき) 一 精神の主体(心)をいう。見たもの、聞いたこと、香り、味、感触とその内容を認識
し、満足や喜びや感動や感謝の心がはたらいて、私たちの「生きる」ことが成り立
ちます。
世界中に食事とその作法の文化があります。私たちのいのちを支え育てる、家庭や社会のなかでの大事な教育です。「不殺生(ふせっしょう)」が仏教徒の生活規範(きはん)の第一ではありますが、私たちは生きるために命あるものを食べなければなりません。野菜や果物は枯(か)れてしまってからでは食べられないし、肉や魚介(ぎょかい)も新鮮なものを求めますが、むやみに殺してはなりません。
食事の前に、眼前の食物や生物(いのち)に向って両の手を合わせ(合掌(がっしょう)一いのちに対する敬意(けいい))、申し訳ありませんが、私の生存のためにあなたのいのちを『いただきます!』と、言わずにおれない伝統のマナーを大事にしなげればならないと思います。
また、この食事が私の前に整うまでの過程と準備への感謝を込めて、手を合わせ『ごちそうさま!』も忘れてはなりません。
世界の国の中で下から14番目の食料自給率(42%)の日本で、食べ物の3割が捨てられているといわれています。
この現実もふまえながら、忘れかけていた豊かな食文化を思わずにはおれません。
世界中に食事とその作法の文化があります。私たちのいのちを支え育てる、家庭や社会のなかでの大事な教育です。「不殺生(ふせっしょう)」が仏教徒の生活規範(きはん)の第一ではありますが、私たちは生きるために命あるものを食べなければなりません。野菜や果物は枯(か)れてしまってからでは食べられないし、肉や魚介(ぎょかい)も新鮮なものを求めますが、むやみに殺してはなりません。
食事の前に、眼前の食物や生物(いのち)に向って両の手を合わせ(合掌(がっしょう)一いのちに対する敬意(けいい))、申し訳ありませんが、私の生存のためにあなたのいのちを『いただきます!』と、言わずにおれない伝統のマナーを大事にしなげればならないと思います。
また、この食事が私の前に整うまでの過程と準備への感謝を込めて、手を合わせ『ごちそうさま!』も忘れてはなりません。
世界の国の中で下から14番目の食料自給率(42%)の日本で、食べ物の3割が捨てられているといわれています。
この現実もふまえながら、忘れかけていた豊かな食文化を思わずにはおれません。
第五十二回
2022-10-03
高齢化社会の一端(いったん)を担(にな)っている私も、歳を重ねるに従い、友人・知人の訃報(ふほう)に接することが多くなりましたが、結婚式などの慶事に招かれることはなくなってしまいました。後は孫の結婚を待つのみです。(間に合うといいのですが。周りからは無理でしょうという声が・・・)
「80年かかってやっと手に入った80歳なのだから、大事に生きなければ」と思う半面、高齢者の多くは「つまらんようになった」と自嘲気味(じちょうぎみ)に本音をもらします。何故そう思わずにはいられないようになっているのか考えてみました。
「80年かかってやっと手に入った80歳なのだから、大事に生きなければ」と思う半面、高齢者の多くは「つまらんようになった」と自嘲気味(じちょうぎみ)に本音をもらします。何故そう思わずにはいられないようになっているのか考えてみました。
戦後77年、わが国は世界有数の高品質製品生産国になり、そのために、木材・石材・鋼材・集成材などあらゆる素材や用材が必要となりました。さらに、知恵も技術も労働も情報も資金もそのための「材」となり、そういうことから「逸材(いつざい)」「適材(てきざい)」「人材」などと、人間が「材」としての価値でみられるようになったのです。
確かに人生の中で、人材と呼ばれるにふさわしい働きをする時期はありますが、私たちは「人材」である前に、「人間」であることを明確にしておかなければなりません。
「人材」とは、何か(誰か)にとって役に立つ、あるいは都合の良い材料としての人間のことですから、いい人材からそうでもないものまで、はっきりと序列・順位が付きます。そして、その役や仕事のための人材として相応(ふさわ)しくなくなると、同じような働きをする他の人が人材として代わるわけです。つまり、人材は代行可能であり、見る人による価値の序列があるものです。
確かに人生の中で、人材と呼ばれるにふさわしい働きをする時期はありますが、私たちは「人材」である前に、「人間」であることを明確にしておかなければなりません。
「人材」とは、何か(誰か)にとって役に立つ、あるいは都合の良い材料としての人間のことですから、いい人材からそうでもないものまで、はっきりと序列・順位が付きます。そして、その役や仕事のための人材として相応(ふさわ)しくなくなると、同じような働きをする他の人が人材として代わるわけです。つまり、人材は代行可能であり、見る人による価値の序列があるものです。
私たちは、生きていれば必ず老い、傷病(しょうびょう)を得、死を迎えます。それに従って、世間的には人材としての価値が下がっていくとみられるので、「つまらん者になった」と嘆くことになります。若い元気な時に、老人や障がいのある人などを価値が低いと蔑視(べっし)していた人ほど、自分がそうなったときに、事実をまっすぐに受け容れにくいようです。
大事なことは、私たちは「人間」であるということです。人間である限り、いのちあるものである限り、無条件に尊いのです。その尊さは、老いや心身の傷病や肉体の不自由などでいささかも減ずるものではありません。全く平等の世界です。
完璧(かんぺき)な人も完成された人も一人もいない、みんな長短を併(あわ)せ持った者同士です。その表れ方はそれぞれで、それが個性となる。だからこそ誰も代わることはできません。不完全なそれぞれが、それぞれに尊く平等なのです。そして不完全であるからこそ、願われているのであり勉強する余地があるのです。成長し続けるのです。また、支え合い、助け合わなければ生きていけないのです。
宗教とか教育というものは、「人間」を育てるものであって、「人材」をつくるものではないのです。もちろん結果として、優れた人材として活躍する人と成ることは素晴らしいことですが、まず人間としてどう成長したかということが大事なことでしょう。
「ヒト」として生まれた私たちが、さまざまな学びと経験を通して、私に安心できる人間性豊かな、自覚的人間に成っていく。そういう必要性を背負って生きていると感じさせられています。
第五十一回
2022-08-31
現代社会の一つの特徴として、「個」の尊重ということがあります。個性や人権を大事にすることはとても大切なことですが、「人それぞれ」をあまり強調し過ぎると、人間として本当に大切なことを見失う方向に進んでしまうということがあるようです。
あらゆることが個別化また個人の利益追求の方向に傾き、便利で快適な個室に居て、知らず知らずのうちに人間として社会と関わることが少なくなってしまう。その姿を「コクピット的全能感(ぜんのうかん)(何でもできる)」を持っていると表現した人がいます。
例えば、戦闘機の操縦席のように、周りの機器やリモコンで座ったまま情報をキャッチ(テレビ、スマホ)し、あらゆるところにアクセス(インターネット)し、まったく痛みや苦痛を感じることなく相手を攻撃(ゲーム)できる。これが私たちの現代文明が日指した姿なのでしょうか。そしてそれは幸せなのでしょうか。
世界には、日本の子どものお年玉以下のお金で、家族全員が1年間生活している人が10億人もいるそうです。その人たちが不幸で、私たちがはるかに幸せとはとても思えないのですが・・・。
今の私たちは、ワガママが通れば通るほど、自分の都合がうまくいって自分の思い通りになればなるほど暗くなっていくようです。満たされたはずなのに何か明るくならない、元気が出ない、そんなふうになっていくようです。
辛(つら)く苦しい状態のことを「地獄」といいますが、その「獄」の字は「ケモノヘン」と「犬」の間に「言」という形です。つまり、ケモノと犬がコミュニケーションしようとするが出来ない姿です。つながりや関係性が切られ孤立させられていくということが、人間にとって一番辛く苦しいことです。
平安時代の僧・源信僧都(げんしんそうず)の著書『往生要集(おうじょうようしゅう)』には「我今帰(き)する所なく、孤独にして同伴(どうはん)なし」と説明されています。安心できる帰る場所がないのが地獄であり、関係性を絶たれて排除(はいじょ)され差別され無視されて、ともに生きたいと体中が願っているのにともに生きともに喜び悲しむ人がいない、それが地獄なのだと。
自分の中に生きる喜びや楽しみや満足感のない人ほど、下方比較(かほうひかく)(自分より下のものを探しそれと比べて満足しようとする)をしたがる。それが差別やいじめやハラスメントなどになっていきます。他の人の人間性を奪うことが、実はその人自身が人間性を失うことになるのです。そんな方向に本当の幸せがあるはずがありません。下方比較によって一層非人間化が進み、なお内からの満足はなくなるという悪循環(あくじゅんかん)に陥(おちい)ってしまいます。
私たちは、自分に利益があることだけが幸せで、他人に物をあげたり分けたりするのは損だという考え方があります。しかしそれは逆なのです。おすそ分けすることができるという幸せ、困っている人に自分のできる限りのことをすることができる幸せというものもあるのでしよう。
犬や猫など動物を表す言葉と異なり、私たちは「間」の上に「人」という字をおいて「人間(じんかん)」といいます。つまり「間柄(あいだがら)」という関係性の上に私たちの一人ひとりの「人」というものが成り立っているということです。
私という「人」の幸せや存在満足は、「間柄」(関係性、共感、挨拶、会話、気遣い、思いやり、親身のふれあい、コミュニケーションなど)があってはじめて成り立つのです。
コクピットから出て、人間の温かさ爽(さわ)やかさを感じてほしいと思います。
あらゆることが個別化また個人の利益追求の方向に傾き、便利で快適な個室に居て、知らず知らずのうちに人間として社会と関わることが少なくなってしまう。その姿を「コクピット的全能感(ぜんのうかん)(何でもできる)」を持っていると表現した人がいます。
例えば、戦闘機の操縦席のように、周りの機器やリモコンで座ったまま情報をキャッチ(テレビ、スマホ)し、あらゆるところにアクセス(インターネット)し、まったく痛みや苦痛を感じることなく相手を攻撃(ゲーム)できる。これが私たちの現代文明が日指した姿なのでしょうか。そしてそれは幸せなのでしょうか。
世界には、日本の子どものお年玉以下のお金で、家族全員が1年間生活している人が10億人もいるそうです。その人たちが不幸で、私たちがはるかに幸せとはとても思えないのですが・・・。
今の私たちは、ワガママが通れば通るほど、自分の都合がうまくいって自分の思い通りになればなるほど暗くなっていくようです。満たされたはずなのに何か明るくならない、元気が出ない、そんなふうになっていくようです。
辛(つら)く苦しい状態のことを「地獄」といいますが、その「獄」の字は「ケモノヘン」と「犬」の間に「言」という形です。つまり、ケモノと犬がコミュニケーションしようとするが出来ない姿です。つながりや関係性が切られ孤立させられていくということが、人間にとって一番辛く苦しいことです。
平安時代の僧・源信僧都(げんしんそうず)の著書『往生要集(おうじょうようしゅう)』には「我今帰(き)する所なく、孤独にして同伴(どうはん)なし」と説明されています。安心できる帰る場所がないのが地獄であり、関係性を絶たれて排除(はいじょ)され差別され無視されて、ともに生きたいと体中が願っているのにともに生きともに喜び悲しむ人がいない、それが地獄なのだと。
自分の中に生きる喜びや楽しみや満足感のない人ほど、下方比較(かほうひかく)(自分より下のものを探しそれと比べて満足しようとする)をしたがる。それが差別やいじめやハラスメントなどになっていきます。他の人の人間性を奪うことが、実はその人自身が人間性を失うことになるのです。そんな方向に本当の幸せがあるはずがありません。下方比較によって一層非人間化が進み、なお内からの満足はなくなるという悪循環(あくじゅんかん)に陥(おちい)ってしまいます。
私たちは、自分に利益があることだけが幸せで、他人に物をあげたり分けたりするのは損だという考え方があります。しかしそれは逆なのです。おすそ分けすることができるという幸せ、困っている人に自分のできる限りのことをすることができる幸せというものもあるのでしよう。
犬や猫など動物を表す言葉と異なり、私たちは「間」の上に「人」という字をおいて「人間(じんかん)」といいます。つまり「間柄(あいだがら)」という関係性の上に私たちの一人ひとりの「人」というものが成り立っているということです。
私という「人」の幸せや存在満足は、「間柄」(関係性、共感、挨拶、会話、気遣い、思いやり、親身のふれあい、コミュニケーションなど)があってはじめて成り立つのです。
コクピットから出て、人間の温かさ爽(さわ)やかさを感じてほしいと思います。