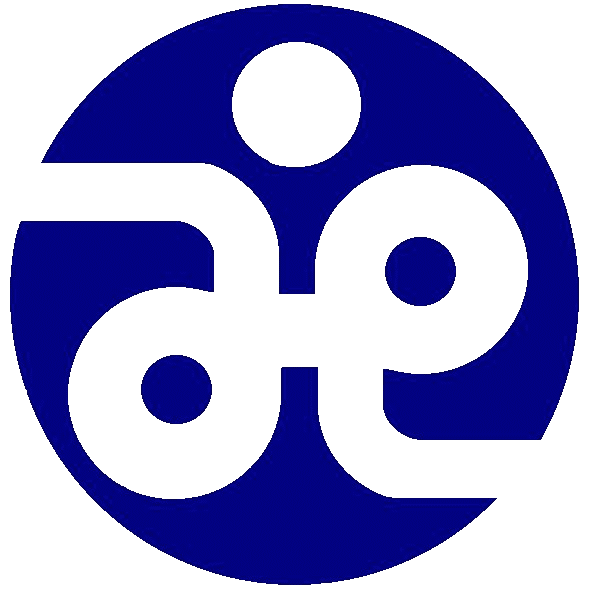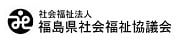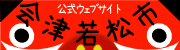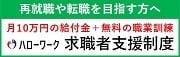会長のつぶやき
会長 武藤淳一
【生年月日】1942年(昭和17年)6月15日
【住まい】福島県会津若松市
【家族構成】妻、長男夫婦、孫2人の6人家族
【本職】寺院住職
【経歴】大学卒業後、教職を経て住職に。PTA役員、民生児童委員等を経験。
【住職として伝えたいこと】
「家庭」「生活」―人間として何をすること(ところ)なのかを学び実践すること
【仕事をする上で気をつけていること】丁寧(心を込めて親切に対応すること)
【座右の銘】身自當之しんじとうし無有代者むうだいしゃ(仏教の言葉)
意味:人生の中で苦しいこと、悲しいことに出会っても、誰も代わってくれないし自ら引き受けて生きていく
【尊敬する人】親鸞
【最近読んだ本】天地明察
第三十回
2020-12-01
私たちは、近年数多くの自然災害や事故、遡(さかのぼ)ると戦禍(せんか)にも見舞われてきました。そして今、新型コロナウイルスの感染という稀(まれ)に見る脅威にさらされています。その度に多くの人命が失われ、大切なものが奪われるという被害を被(こうむ)ってきました。
そして各地では、その犠牲者を悼(いた)み追弔法会(ついちょうほうかい)が執り行われていますが、実はこの追弔会法要(ついちょうかいほうよう)ということは、ただ単に亡くなられた方々を偲(しの)んだり、供養したりすることだけではないのです。
普通私たちは、「時」ということを考えるとき、「過去・現在・未来」という流れで受けとめていますが、仏教では「過去・未来・現在」というとらえ方をします。
今日(こんにち)の私たちは、過去に起きた災害や事故や戦争という出来事から、「私たちの犠牲を無駄にしてくれるな」と過去から深く願われている、そういう責任を担(にな)って生きているのでしょう。
同時に、私たちの今さえよければということで、何もかも使い尽くし利用し尽くしている現在の生活が、未来からおそらくは「あなたたちは未来のことをどう考えてきた」のか、「子や孫にどんな未来を残そうとしてきた」のか、と問われている、そういう過去と未来に問われている”現在(いま)“を生きているのでしょう。
亡き人を偲び法要を営むということは、過去と未来からの問いかけに気付かされる「学びの場」をいただくという大切な意味も持っているのです。
人間というものは、他の生き物とは違います。いろいろな違いがありますが、人間は人間に育てられないと人間になれないのです。
人間は未完成で、未熟なままで生まれてきます。ですから、何に出会い何を学ぶかによって大きく変わります。
犬や猫は完成されて生まれてきます。家で人間に飼われたり、動物園で飼育係に育てられたので、気がついたら人間になっていたということはありません。変わらないのです。
人間は、出会ったこと(もの)学んだこと(もの)によって、すなわち出会った縁(環境)によって変わるのです。環境次第でどうにでも変わってしまうのが人間なのです。
そういう意味では、人間は課題的存在といえます。まさに過去と未来から問われて、課題を生きていくものなのです。
ところが、私たちはその課題を忘れて、日常の目の前のことにとらわれそれに振り回されていくので、なかなかそういうことに気づきません。だからこそ、常に本来の在り方に引き戻してくれる”はたらき”に出会うことが、何よりも大切なことなのです。
今起こっている様々な出来事を通して、改めてそういうことを学び直し考えさせていただいて、本当の意味で”人間”を生きて往きたいと思います。
第二十九回
2020-09-01
ついに恐れていた新型コロナウイルス感染が、会津若松市でも現実のこととなってしまいました。「会津での第1号感染者にはなりたくない」と、注意しながらの生活でしたが、残念ながら当市も例外を通すことはできませんでした。
誠に辛いことですが、これからもさらに気を引き締めて、蔓延まんえんを防ぐ手立てを講じていかなければならなくなりました。
このところ私たちの身の周りでは、地球規模で様々な災害や病気など異常事態が頻繁ひんぱんに起こっています。多くの研究者が指摘し続けている、地球を取り巻く環境の悪化が、目に見える形で現れているようです。
人類が長年に亘って追求してきた、豊かさ、便利で快適な暮らしの享受きょうじゅが、気づかないうちに地球全体の環境を汚染し、大気を汚し、宇宙空間までゴミでいっぱいに満たしてしまいました。そして人間はもとより、すべての命の存続さえ危うい状態にしてしまったのです。
私たちの身の周りに起こるすべてのことには原因があり、そのことが結果としてあらわれてくる、これは誰にも変えることも、動かすこともできない絶対の真理、真実です。
人類がこの地球上に誕生して以来、願い続け、行動し続けてきた事実の積み重ねが、今結果として私たちの身の周りに現われてきているということでしょう。
何時の日か、すべての人類がこの現実に目覚め、どうすればより良い”原因”をつくっていくことができるのか真剣に考え、取り組んでいかなければならない「時代とき」を生きているのだと改めて思い知らされています。
第二十八回
2020-06-04
新型コロナウイルスの蔓延まんえんにより、私たちの生活は一変しました。
その恐怖と不自由さの中でも懸命に闘い、生きるための努力を尽くしている人々の姿が、連日報ぜられています。その尊い姿に励まされながら、日々を過ごさせていただいています。
私の家にどういう経緯けいいで伝わったのかわかりませんが、石の小さなお地蔵様がおられます。庭石の上に安置しておいたのですが、気づいた方がお賽銭をあげてお参りをしていかれるのです。
ある時ふと気づかされたのですが、よく見るとお地蔵さまは合掌しておられるのです。普段は、恥ずかしながらお賽銭の方ばかりに気をとられ、お地蔵様にはあまり関心を示さず、その存在すら忘れているこの私に向かって、両の手を合わせ静かに微笑ほほえみをたたえながら拝んでおられるのです。拝む人も、気づかずに通り過ぎていく人も、いつも拝んでくださっているのです。
でも、拝まれているのは”私”ではありません。私が内包ないほうする”尊さ”に礼拝して下さっているのでしょう。私の自覚を超えた、私の尊さが拝まれていたのでしょう。拝まれて知らされる私の尊さがあったということです。拝み拝まれるということによって、尊い者同士であったと知らされるのです。
「覚さとり」とは、自分を含めた一切の尊さに目覚めることかもしれません。全ての存在には意味があり、価値があり、そしてつながり関係している故に、あらゆる存在や現象が私を支え成り立たせ、同時に私も何かを支え成り立たせている大事な存在なのだ、と気づいていくということなのでしょう。
その尊い私は、私を尊く生きているでしょうか?
他の命の尊さが見えず、私の都合のために他を利用し貶おとしめていく。そのことによって、さらに私自身の尊さが見えなくなっているのではないか。それを感じる力を「宗教心」というのでしょう。宗教(真実の教え)によってそういう私に気づき、その恥ずかしい私が、尊い存在として願われ支えられていると知らされるのです。そこに感謝と喜びと痛みが生まれます。その上で、たとえそれがささやかであっても、自らに与えられた環境条件の中で、できることを尽くしていく生活が始まるのでしょう。
尊さを見失ったとき、いじめ、差別、虐待、排除のような、他者の人間性を見失う姿になります。その他者を非人間化した時、自分自身が人間性を失い、非人間化してしまうのです。戦も争も殺も傷もそこから始まります。
第二十七回
2020-04-17
新型コロナウイル大の感染が止まりません。多くの方が感染し命を失っています。感染者の治療に日夜心血を注いでおられる医療関係者のお姿には本当に頭が下がります。不要不急の外出を控えるため種々の行事等が中止になり、毎日家の中で過ごすことが多くなりました。働いている方には大変申し訳ありませんが…。
日本でも、海外でも様々な憂うべき出来事が起き、不安に駆られた人間の行動の恐ろしさが現出しています。こうした時には必ずと言っていいほど各鐘のデマが流れます。一部の心無い人による言動が、この一大事に真撃に向き合い働く人達をどれだけ傷つけているかと思うと心が痛みます。
物流を止めないために物資を運ぶ運転手さん、感染者の治療にあたっている病院勤務の方々など。それらの人々に向けられる迫害の数々が報じられるたびに何ともやりきれない気持ちにさせられます。
しかし、一方では、感謝の気持ちを表し応援の声を上げる運動もみられ、救われる思いもあります。ぜひともこの運動の広がりを期待したいと思います。
私たちは、この世(娑婆しゃば「シヤーバ」の音写、漢訳「堪忍土かんにんど=耐え忍ばなければならない世界」)を生きています。
出来れば快適に幸福に生きたいということで、その妨げになりそうなものをできる限り排除しようとしてきました。不快、不便、貧困、危険、不健康等々。つまり「四苦八苦しくはっく」と言われるようなものを、その苦に出会う前から遠ざけようと努力してきたわけです。
老化を遅らせ、病気を予防するための薬や健康食品、健康グッズなどに異常なほどの関心を持ち、また損をしないように他人より下にならないように、そして死なないように死なないようにしてきたようです。ですから、老・病・死を我々に見せつけずにはいられないようなものを遠ざけ、また差別せずにはいられないのです。
このように、生きる妨げを事前に取り除くことには熱心ですが、果たして「今を生きる」というそのことを積極的にしているのでしょうか。例え劣悪れつあくな環境や条件の中でも生きていく力を、育てようとしてきたのでしょうか。本来私たちに備わっている力のはずです。
ある方が常々、「私は本当にやりたいこと一つをやるために、いやなことを百やる」、とおっしゃっています。
やりたいことがはっきりすると、元気も勇気も出てきます。困難があろうと障害が予想されようと、意欲をもって臨めば、必ず手応てごたえのある生き方が開けてきます。自分にとって都合よくならなくても、遠回りになっても、その行いの全ては意味のあるものになるはずです。苦を減らすことだけでなく、いきいきと「生」を輝かせたいものです。
第二十六回
2020-03-11
「啐啄同時そったくどうじ」(鶏の卵がかえるとき、「啐」は殻からの内から雛ひながつつく、同時に「啄」は母鶏が殻の外から同じところをつつく)という言葉があります。
外からの刺激や情報と内からのはたらきの接点に、「学び」が実現するということを喩たとえた言葉で、師匠の教える力と共に生徒が「学ぶ力」を身につけなければ、十分に学力を身につけることができないということをあらわしています。
一口に「学力」と言いますが、「学力」とは何を指すのでしょう。
一般的には、どのくらい知識や技能を身につけたかという、結果としての「学んだ力」を指しています。
しかし、「学ぶ力」ということは、教わったこと出会ったこと与えられた情報などを、いかに力として吸収するか、身につけるかという力のことをいうのだと思います。
また、「学ぼうとする力」は関心の向きというか、意思をもってさらに学ぶ姿勢というか、そういうものでしょう。
自分では意識していない学びもあります。日常の生活の中で、知らず知らず染しみ込んでいく多くのことがあります。
例えば言葉の環境です。感謝や喜び、尊敬、信頼の言葉(ありがとう、いただきます、もったいない、おはよう、こんにちはなど…)の交わされる中に生活するのか、批判や愚痴ぐち、攻撃の言葉が飛び交う中で育つのか、大きな違いになっていきます。周りの大人たちがよく勉強すると子どもたちもよく勉強します。
「弟子の準備ができると、師が現れる」と言われます。学ぼうという意欲があり学ぶ力さえあれば、あらゆるものごとから気づき学ぶことを見つけて、そこから思惟しゅい(考えること)が始まり深まり、言動となります。
学ぶ姿勢とは、出会ったもの学んだことから自分自身を正しく知り、それによって自分の内にあるものが顕在化けんざいかする、すなわち生き方が変革することになっていく。生きる姿勢が変わるのです。
大人も子供も、今自分に与えられている能力資質感性を眠らせることなく、学ぶ姿勢をもって「啐啄同時そったくどうじ」の成長の瞬間を積み重ねてほしいものです。