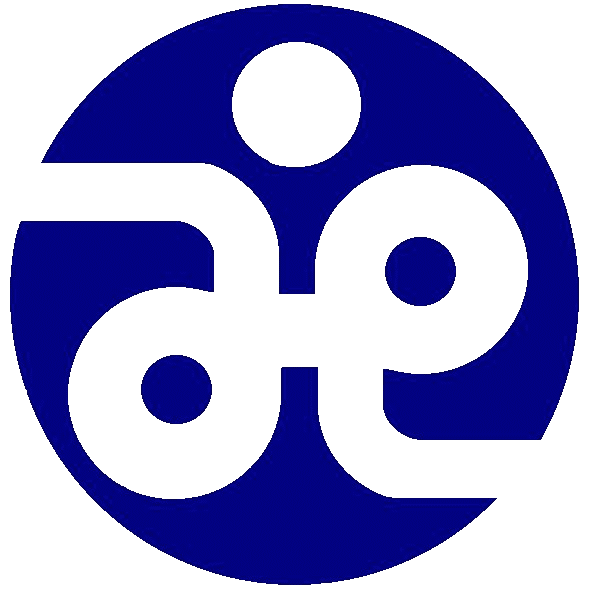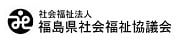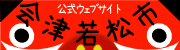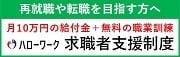会長のつぶやき
会長 武藤淳一
【生年月日】1942年(昭和17年)6月15日
【住まい】福島県会津若松市
【家族構成】妻、長男夫婦、孫2人の6人家族
【本職】寺院住職
【経歴】大学卒業後、教職を経て住職に。PTA役員、民生児童委員等を経験。
【住職として伝えたいこと】
「家庭」「生活」―人間として何をすること(ところ)なのかを学び実践すること
【仕事をする上で気をつけていること】丁寧(心を込めて親切に対応すること)
【座右の銘】身自當之しんじとうし無有代者むうだいしゃ(仏教の言葉)
意味:人生の中で苦しいこと、悲しいことに出会っても、誰も代わってくれないし自ら引き受けて生きていく
【尊敬する人】親鸞
【最近読んだ本】天地明察
第四十五回
2022-03-01
今年も各地で成人式が行われました。
このコロナ禍の中で制約を受けての式典のようでしたが、それでも「新成人」と呼ばれ、晴れやかな笑顔で式に臨む姿は、初々しくまた頼もしくも感じられました。
国では「おとな」になる年齢を18歳に引き下げるということで、さまざまな議論がなされているようです。社会生活の中で「おとな」として扱われるということは、実に多くの責任ある行動が求められます。18歳という年齢が、そのことに耐えうるものかどうかは意見の分かれるところでしょう。
改めて「成人式」とはどういう行事なのか、考えてみたいと思います。
「成人」とは、「人と成る」すなわち「人間完成」ということですが、現実には20歳で文字通りの「人間完成」とは言えないようです。
国では「おとな」になる年齢を18歳に引き下げるということで、さまざまな議論がなされているようです。社会生活の中で「おとな」として扱われるということは、実に多くの責任ある行動が求められます。18歳という年齢が、そのことに耐えうるものかどうかは意見の分かれるところでしょう。
改めて「成人式」とはどういう行事なのか、考えてみたいと思います。
「成人」とは、「人と成る」すなわち「人間完成」ということですが、現実には20歳で文字通りの「人間完成」とは言えないようです。
ではなぜ20歳を「成人式」として祝うのでしょうか。
ある先生の言葉をお借りすると、"それまで親や先生や周りの大人たちによって成長させられてきた者が、「自分の意志で、人間として完成する方向に歩み始めるぞ」と決意をする行事"だということです。
自分が人間として生まれたことの意味や価値に気づき、また周りの全ての事柄とのかかわりの中で生きていることを自覚して、「人間成就」に向かって歩みを始める決意をする。なりたい自分になるために、自己実現のためにと言ってもいい、その歩みの原動力として自分の意志・意欲を呼び覚ます。そういう一つの区切り目となる自覚のための行事だろうと思います。
社会人(おとな)の基本は「返事、挨拶、後始末」であると聞いたことがあります。
例えば掃除一つをとってみても、部屋がいかにきれいになったかということはもちろん大事ですが、それよりも意欲をもって掃除しようとする人、自主的に掃除する人、少しでもきれいになるように掃除しようとする人、汚さない人という「人」になることが求められているのでしよう。
他人の目や評価や厳しい指導によってということから、自分で判断して自発的に掃除することを思いつく人に成ってほしいものです。
「成人」ということは、年齢に関わりなくいくつになっても、自分の課題を意識して「人と成る人」として歩み続けることだろうと思います。
ある先生の言葉をお借りすると、"それまで親や先生や周りの大人たちによって成長させられてきた者が、「自分の意志で、人間として完成する方向に歩み始めるぞ」と決意をする行事"だということです。
自分が人間として生まれたことの意味や価値に気づき、また周りの全ての事柄とのかかわりの中で生きていることを自覚して、「人間成就」に向かって歩みを始める決意をする。なりたい自分になるために、自己実現のためにと言ってもいい、その歩みの原動力として自分の意志・意欲を呼び覚ます。そういう一つの区切り目となる自覚のための行事だろうと思います。
社会人(おとな)の基本は「返事、挨拶、後始末」であると聞いたことがあります。
例えば掃除一つをとってみても、部屋がいかにきれいになったかということはもちろん大事ですが、それよりも意欲をもって掃除しようとする人、自主的に掃除する人、少しでもきれいになるように掃除しようとする人、汚さない人という「人」になることが求められているのでしよう。
他人の目や評価や厳しい指導によってということから、自分で判断して自発的に掃除することを思いつく人に成ってほしいものです。
「成人」ということは、年齢に関わりなくいくつになっても、自分の課題を意識して「人と成る人」として歩み続けることだろうと思います。
第四十四回
2022-02-01
一時収まりかけた新型コロナウイルス感染でしたが、このところ変異したオミクロン株により、再び急激な感染の広がりを見せています。感染経路が不明な(発表されない?)状態で、子どもたちに蔓延(まんえん)し、特に仕事を持つ母親に大きな不安と負担を強いているようです。
国をはじめとする行政や医療機関では、その対策に必死で取り組んでいただいておりますが、私たちもどれだげその指示に従って協力(これは他人ごとではないのですが・・・)していけるかが問われていると思います。
国内外で、"ワクチンを接種しない自由""マスクを着用しない自由"(持病等は別)などと声高に主張している人々の姿が報じられていますが、そういうことが「自由」の中身なのでしょうか。カラオケや飲み会への参加など、コロナの感染はその人個人だけで済(す)む問題なのでしょうか・・・。
この頃、見ず知らずの他人を巻き込んでの、いわれのない殺人や放火事件が続けざまに起きています。自分の思い通りにならない不平不満を、他人を巻き添えにして晴らそうとする身勝手な犯行は、決して許されない所業(しょぎょう)であり、たまたまそこに居合わせて犠牲になった人たちにはかける言葉もありません。
仏教に説かれる、基本的生活規範(きはん)として「五戒(ごかい)」が教えられています。その第1は「不殺生(ふせっしょう)」です。生きようとするものを殺したり傷つけたりすることから遠ざかれという戒(いまし)めです。
「殺生」はまた五つに分けられています。
1、「自殺(じせつ)」 - 自らを殺してはいけないということ。
国をはじめとする行政や医療機関では、その対策に必死で取り組んでいただいておりますが、私たちもどれだげその指示に従って協力(これは他人ごとではないのですが・・・)していけるかが問われていると思います。
国内外で、"ワクチンを接種しない自由""マスクを着用しない自由"(持病等は別)などと声高に主張している人々の姿が報じられていますが、そういうことが「自由」の中身なのでしょうか。カラオケや飲み会への参加など、コロナの感染はその人個人だけで済(す)む問題なのでしょうか・・・。
この頃、見ず知らずの他人を巻き込んでの、いわれのない殺人や放火事件が続けざまに起きています。自分の思い通りにならない不平不満を、他人を巻き添えにして晴らそうとする身勝手な犯行は、決して許されない所業(しょぎょう)であり、たまたまそこに居合わせて犠牲になった人たちにはかける言葉もありません。
仏教に説かれる、基本的生活規範(きはん)として「五戒(ごかい)」が教えられています。その第1は「不殺生(ふせっしょう)」です。生きようとするものを殺したり傷つけたりすることから遠ざかれという戒(いまし)めです。
「殺生」はまた五つに分けられています。
1、「自殺(じせつ)」 - 自らを殺してはいけないということ。
振り返ってみると、自分の中にあるいきいきと生きようとする願いを、自分で妨げているということはないでしょうか。
2、「他殺(たせつ)」 - 他人のいきいきと生きたいという願い、希望を殺す(奪う)こと。
嫌(いや)がらせ、いじめ、誹誇中傷(ひぼうちゅうしょう)、パワハラ、差別などによって相手の心を傷つけ、生きる意欲や希望を無意識にでも奪ってしまったことはないでしょうか。
3、「方便殺(ほうべんせつ)」 - 直接に手を下すことはなくても、他人や方法を使って辛(つら)い目に合うように仕向(しむ)けること。
例えば、振り込め詐欺(さぎ)など。
4、「歓喜殺(かんぎせつ)」 - 他人が死んだり、生きる意欲をなくしたりすることを喜ぶということ。「愉快(ゆかい)犯」。
例えば、戦争は、敵国の兵士や国民が死に、傷つき、敗れることを望み喜ぶこともあるのでしょう。
5、「呪殺(じゅせつ)」 - 恨(うら)んだり憎(にく)んだりする人の死を願うこと。
「あんな人いなくなればいいのに」「あいつさえいなくなれば幸せになるのに」などと思ったことはありませんか。
自分を深く見つめてみると、誰でも思い当たることの一つや二つはあるのではないでしょうか。私たちが生きるということは「ともに生きる」ということなのですが、そのことに気付くことは意外に難しいことのようです。
2、「他殺(たせつ)」 - 他人のいきいきと生きたいという願い、希望を殺す(奪う)こと。
嫌(いや)がらせ、いじめ、誹誇中傷(ひぼうちゅうしょう)、パワハラ、差別などによって相手の心を傷つけ、生きる意欲や希望を無意識にでも奪ってしまったことはないでしょうか。
3、「方便殺(ほうべんせつ)」 - 直接に手を下すことはなくても、他人や方法を使って辛(つら)い目に合うように仕向(しむ)けること。
例えば、振り込め詐欺(さぎ)など。
4、「歓喜殺(かんぎせつ)」 - 他人が死んだり、生きる意欲をなくしたりすることを喜ぶということ。「愉快(ゆかい)犯」。
例えば、戦争は、敵国の兵士や国民が死に、傷つき、敗れることを望み喜ぶこともあるのでしょう。
5、「呪殺(じゅせつ)」 - 恨(うら)んだり憎(にく)んだりする人の死を願うこと。
「あんな人いなくなればいいのに」「あいつさえいなくなれば幸せになるのに」などと思ったことはありませんか。
自分を深く見つめてみると、誰でも思い当たることの一つや二つはあるのではないでしょうか。私たちが生きるということは「ともに生きる」ということなのですが、そのことに気付くことは意外に難しいことのようです。
第四十三回(年頭挨拶)
2022-01-06
新年明けましておめでとうございます。
令和四年の新春は、寒さの厳しい雪のお正月となりましたが、皆様方におかれましては、どのような元旦を迎えられたでしょうか。
このコロナ禍による長期自粛生活により、精神的にも経済的にも辛い不自由な生活を強いられている方々には心よりお見舞い申し上げます。
県内各地では、感染も減少し安心しかけたところでしたが、また新たなウイルスによる感染が広がりはじめてしまいました。この分では、今年も不本意ながら、予防対策の手を緩めずに取り組まなければならない状況に変わりはないようです。
昨年も本会では、すべての事業において規模を縮小し、感染予防に努めながら事業を推進して参りました。おかげ様をもちまして、職員全員が持てる力を結集して事業に取り組み、それなりの成果を上げることができたと自負しております。これもひとえに市民の皆様のご支援ご協力があってのことと、誠に有り難く、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
さて、私たちを取り巻く社会情勢は、少子高齢化による人口減少傾向が進む中、人と人とのつながりの希薄化が心配されています。
さらに、コロナ禍がそれに拍車をかけるように、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼしています。
そのような状況を少しでも改善するために、地域の力で地域内の福祉課題を掘り起こし、自分たちの力で解決が難しい問題は、行政や社協につなぐという役割を担っていただく"地区社協"の設置に取り組んでおります。
幸いにも昨年10月謹教地区に、市内5カ所目となる「謹教ふれあいネットワーク」が設立されました。このことは、今後他地区での設立に向けて弾みがつくと同時に、地域での福祉活動に大きな力となることが期待されるところであります。
コロナ感染の収束が見えない状況ではありますが、今年も皆様方のご要望に少しでも応えられる社協を目指して、職員一同真撃(しんし)に課題に取り組んでいく所存(しょぞん)であります。
市民の皆様には更に一層のご理解とご協力をお願い申し上げるとともに、一日も早いコロナ感染収束を願いまして新年のご挨拶とさせていただきます。
第四十二回
2021-12-20
ここ数年地球温暖化の影響と思われる災害が頻繁(ひんぱん)に起き、その度に甚大(じんだい)な被害を被(こうむ)っています。世界中の指導者が、その対策について議論を重ねていますが、結局は自国の利益を最優先する立場を離れることはできないようです。
私たちが、より便利で快適な生活を求め、その欲望を満たそうとすればするほど、地球やそこに生きる命を脅(おびや)かす方向へと突き進まざるを得ないという結果を招いています。人類の発展が、好むと好まざるとにかかわらず、すべての存在を危(あや)うくしてしまうことを、もはや止めることはできないのでしょうか。
以前「不如意(ふにょい)」(意の如くならず、思い通りにならない)ということについて書いたことがありました。
仏陀釈尊が覚(さと)られた真理は、「縁起(えんぎ)の理法(りほう)」といわれる仏教の根本原理です。「縁起」とは「縁によって起こる」ということで、あらゆる物事は、どんな事でもそのことだけ単独で存在するということはあり得ません。全て関係し合うことで成り立っているということです。私たち一人ひとりも勿論(もちろん)関係性の中に生存しています。世の中に私に関係ないものなどないのです。言い換えると、全てはつながっているのです。私は、私以外の全てに支えられ、そして支えているのです。
しかし、関係性の中にあるということは、物事は必ずしも自分の思い通りには進まないことを意味します。
自分では知ることもできない数多(あまた)の条件(縁)によって、現在も未来も成り立つわけですから、自分に都合良くばかりになるはずがありません。それを「不如意」と言います。
天気一つ思い通りになりません。降る条件が整えば雨が降り、照る条件になれば晴れます。ですから私たちが人生を生きるとは、不如意を生きることになります。そして、私たちの都合や願望と、不如意である現実とのギャップが「苦」となります。釈尊が「人生は苦なり」と語られたのは、不如意の現実を思い通りにせずには収まりがつかない私たちを、言い当てられた言葉なのでしょう。
親も子も互いに選ぶことはできません。老化せずに長生きしたいといいますが、できるでしようか?不便や不快や不足は価値が低いからと改善しようとし、不如意に直面することを少なくしようと努めてきました。
「ともに生きる」とは、不如意を生きることです。目を逸(そ)らさないことです。「思い通りにはならないが、成るようには成る」のです。
不如意の現実をきちんと受け止めることが、目覚めのスタートです。思い通りにならない現実から逃避(とうひ)せず、そこで感じ、考える。そのことが私を本当の私にしてくれるのでしょう。
私たちが、より便利で快適な生活を求め、その欲望を満たそうとすればするほど、地球やそこに生きる命を脅(おびや)かす方向へと突き進まざるを得ないという結果を招いています。人類の発展が、好むと好まざるとにかかわらず、すべての存在を危(あや)うくしてしまうことを、もはや止めることはできないのでしょうか。
以前「不如意(ふにょい)」(意の如くならず、思い通りにならない)ということについて書いたことがありました。
仏陀釈尊が覚(さと)られた真理は、「縁起(えんぎ)の理法(りほう)」といわれる仏教の根本原理です。「縁起」とは「縁によって起こる」ということで、あらゆる物事は、どんな事でもそのことだけ単独で存在するということはあり得ません。全て関係し合うことで成り立っているということです。私たち一人ひとりも勿論(もちろん)関係性の中に生存しています。世の中に私に関係ないものなどないのです。言い換えると、全てはつながっているのです。私は、私以外の全てに支えられ、そして支えているのです。
しかし、関係性の中にあるということは、物事は必ずしも自分の思い通りには進まないことを意味します。
自分では知ることもできない数多(あまた)の条件(縁)によって、現在も未来も成り立つわけですから、自分に都合良くばかりになるはずがありません。それを「不如意」と言います。
天気一つ思い通りになりません。降る条件が整えば雨が降り、照る条件になれば晴れます。ですから私たちが人生を生きるとは、不如意を生きることになります。そして、私たちの都合や願望と、不如意である現実とのギャップが「苦」となります。釈尊が「人生は苦なり」と語られたのは、不如意の現実を思い通りにせずには収まりがつかない私たちを、言い当てられた言葉なのでしょう。
親も子も互いに選ぶことはできません。老化せずに長生きしたいといいますが、できるでしようか?不便や不快や不足は価値が低いからと改善しようとし、不如意に直面することを少なくしようと努めてきました。
「ともに生きる」とは、不如意を生きることです。目を逸(そ)らさないことです。「思い通りにはならないが、成るようには成る」のです。
不如意の現実をきちんと受け止めることが、目覚めのスタートです。思い通りにならない現実から逃避(とうひ)せず、そこで感じ、考える。そのことが私を本当の私にしてくれるのでしょう。
第四十一回
2021-11-15
近年とみに命が軽く扱われる事件が多発しているように感じられます。皆、口では命の大切さを唱えていますが、現実には「いのち」の意味を問うことも学ぶこともなく、非常に粗末(そまつ)にされていると思われてなりません。
自分の思い通りにならない不満や不安を不特定多数の人にぶつけ、意味のない迷惑を振りまいて何の痛痒(つうよう)も感じない、そういう感覚が増えていくのではないかと空恐ろしい思いを強くしています。
執拗(しつよう)に繰り返されるいじめを受け、地獄の苦しみに耐えきれず必死にSOSを発信しているにもかかわらず、そのことを受けとめることもせず自殺に追い込んでしまうケースや、事件に遭(あ)っていのちを失った人の家族に対する、SNS等での誹誇中傷(ひぼうちゅうしょう)の中身や数の多さにはただただ驚きあきれるばかりです。
また、歩きスマホによる事故の多さと、その後遺症に苦しむ人たちの様子や後悔する姿とメッセージが報じられるなど、インターネット、パソコン、スマホ等の過剰(かじょう)なまでの普及発展が、人間の心や身体を蝕(むしば)み、社会生活に及ぼしている悪影響ははかり知れないものがあるようです。私たちは、手軽に手にした便利さに振り回され、逆に不幸を招くという皮肉な現実に曝(さら)されているようです。
「いのち」は、生まれたくて生まれ、生きたい、成長したい、わかり合いたい、つながりたいと生きているに違いないのです。しかし、そのいのちの管理人ともいうべき「私」は、生まれて生きる意義や方向を見失ってしまっているようです。
命がその人の母胎(ぼたい)に宿り、そして人間として誕生した。つまりこの私は、いのちに選ばれて生まれ、今、いのちをお預(あず)かりして生きているのです。そして、同じ生きるのなら人格ある人間として「私」として生きたい。「私」としてあらゆるいのちと共にいきいきと生きたいということを、心の底で願っているのでしよう。生きたいのです。殺したくも殺されたくもないのです。
「いのち」とは、生きようとする願いや働きや力のことだと思います。
自分の思い通りにならない不満や不安を不特定多数の人にぶつけ、意味のない迷惑を振りまいて何の痛痒(つうよう)も感じない、そういう感覚が増えていくのではないかと空恐ろしい思いを強くしています。
執拗(しつよう)に繰り返されるいじめを受け、地獄の苦しみに耐えきれず必死にSOSを発信しているにもかかわらず、そのことを受けとめることもせず自殺に追い込んでしまうケースや、事件に遭(あ)っていのちを失った人の家族に対する、SNS等での誹誇中傷(ひぼうちゅうしょう)の中身や数の多さにはただただ驚きあきれるばかりです。
また、歩きスマホによる事故の多さと、その後遺症に苦しむ人たちの様子や後悔する姿とメッセージが報じられるなど、インターネット、パソコン、スマホ等の過剰(かじょう)なまでの普及発展が、人間の心や身体を蝕(むしば)み、社会生活に及ぼしている悪影響ははかり知れないものがあるようです。私たちは、手軽に手にした便利さに振り回され、逆に不幸を招くという皮肉な現実に曝(さら)されているようです。
「いのち」は、生まれたくて生まれ、生きたい、成長したい、わかり合いたい、つながりたいと生きているに違いないのです。しかし、そのいのちの管理人ともいうべき「私」は、生まれて生きる意義や方向を見失ってしまっているようです。
命がその人の母胎(ぼたい)に宿り、そして人間として誕生した。つまりこの私は、いのちに選ばれて生まれ、今、いのちをお預(あず)かりして生きているのです。そして、同じ生きるのなら人格ある人間として「私」として生きたい。「私」としてあらゆるいのちと共にいきいきと生きたいということを、心の底で願っているのでしよう。生きたいのです。殺したくも殺されたくもないのです。
「いのち」とは、生きようとする願いや働きや力のことだと思います。
そしてあらゆる「いのち」は、つながりながらいきいきと響(ひび)き合い、生かしあう世界(これを「極楽」、「浄土」という言葉で表現したのです)へと向かっている。そういう点で「いのち」は「仏性(ぶっしょう)(真実の在り方を求める潜在力(せんざいりょく))」であり、私たちはそういうものを備(そな)えて今を生きているということです。
ですから、私が私として生きるとは、「私 事(わたくしごと)」ではありません。いのちを含めた私を私有化(しゆうか)することは許されません。いわば「公共的(こうきょうてき)な私」を生きているのですから、人間として生きる責任があるのです。そのいのちは、私の人生を通してどうなりたいと、どうありたいと願っているのでしょう。
ですから、私が私として生きるとは、「私 事(わたくしごと)」ではありません。いのちを含めた私を私有化(しゆうか)することは許されません。いわば「公共的(こうきょうてき)な私」を生きているのですから、人間として生きる責任があるのです。そのいのちは、私の人生を通してどうなりたいと、どうありたいと願っているのでしょう。
日常の生活の中で、時に感動を共有し深く共感する経験をします。そんな時、今日(こんにち)まで生きていればこそ出会えたと思います。生きることは出会いです。それは、自分の外にあるものとの出会いもありますが、自分自身に感動をもって出会うこともあるのです。
星野富弘さんの有名な詩があります。
いのちが 一番大切だと
思っていたころ
生きるのが 苦しかった
いのちより大切なものが
あると知った日
生きているのが
嬉しかった
(『《花の詩画集》鈴の鳴る道』偕成社)
様々な環境条件の中で、この私が現に生きていると「今」を自覚した時、自(みずか)らの内から、私としてあらゆるいのちと共にいきいきと生きたいという、いのちから私への呼びかけが聞こえてくるでしょう。
星野富弘さんの有名な詩があります。
いのちが 一番大切だと
思っていたころ
生きるのが 苦しかった
いのちより大切なものが
あると知った日
生きているのが
嬉しかった
(『《花の詩画集》鈴の鳴る道』偕成社)
様々な環境条件の中で、この私が現に生きていると「今」を自覚した時、自(みずか)らの内から、私としてあらゆるいのちと共にいきいきと生きたいという、いのちから私への呼びかけが聞こえてくるでしょう。